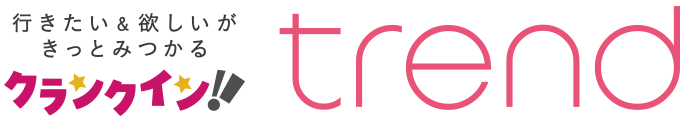オークションに推定3億円の“金の茶道具”が出品! なんでそんなに高いのか調べてみた
Shinwa Auctionが、5月27日(土)に東京・丸の内「丸ビルホール」にて特別オークションを開催する。興味本位で出品リストを眺めてみたところ…「え!」思わず声が出た。一際目をひく「金茶道具一式」のエスティメイト(落札見積価格)がなんと1億5000万円~3億円。到底庶民には手の届かない値段だが、なぜ(「金」とはいえ…)茶道具がこんなに高いのか…。Shinwa Auctionの発表をもとに詳細を調べてみたので、紹介していきたい。
【写真】貴重な作品が出品! 「Shinwa Auction」過去の開催時のイメージ
■藤堂伯爵家伝来の名宝
1929(昭和4)年3月、東京・上野の東京府美術館において、閑院宮載仁親王(かんいんのみやことひとしんのう)を総裁とし、読売新聞社が主催する美術展覧会「日本名寶展覽會」が開催された。この展覧会は、国宝や重要文化財、皇室の御物とともに、華族などの格式の高い名家に伝来し、門外不出とされてきた美術品の数々が一堂に会し、大きな話題となったそうだ。
その優れた名宝の中でも、1ヵ月間ほどの会期中に最も来場者の注目を集めたと言われる出品作品の一つが、この黄金色に輝く金の茶道具一式であった。
当時、この茶道具は伯爵藤堂高紹(とうどうたかつぐ)の所蔵品であり、藤堂家の当主でさえも年に一度しか目にすることのできない秘蔵の家宝だったそうだ。(引用:読売新聞社『日本名寶物語』誠文堂 1929年)
藤堂家は、室町時代に近江国犬上郡藤堂村(現在の滋賀県犬上郡甲良町)とその周辺の地域を治め、江戸時代には藤堂高虎が伊勢国津藩(現在の三重県津市)初代藩主となり、明治時代に伯爵に叙任された家柄。金の茶道具はこの藤堂家に代々伝わり、「日本名寶展覽會」で広く世に知られて脚光を浴びた重宝であるが、第二次世界大戦中の金属類回収令を受けて供出され、日本銀行の買い取りとなったそうだ。
しかし幸運にも、茶道具は武器製造の資源として使用されず、終戦後も日本銀行に残されていたため、1960年に売り戻され、再び藤堂家の所蔵となった。
由緒正しくも数奇な運命をたどったこの金の茶道具一式。いつの時代に、誰が、誰のために制作したものであるのかは詳らかではないそうだが、現代では想像すらできないほどの“歴史”が詰まっており、このエピソードを聞くと前述の値段にも不思議と納得してきた。
もちろん作品としての価値も高く、黄金の輝きばかりに注目してしまうが、一つ一つの造形や、施された文様は非常に精緻で優美。写真からもその美しさが伝わってくる。
また、戦時中に日本銀行が本作を買い取った際に行った金の品位測定によると、おおよそ金80~88%、銀12~20%などの合金で制作されているそう。徳川美術館蔵の「純金台子皆具」が現存する皆具(同じ材質や色味で揃えられた茶道具一式)として重要文化財に指定されているが、本作はもう一つのきわめて重要な作品と言われている。
大量の金を使用し、優れた腕を持つ者に制作を依頼することのできる注文主の財力と政治力―― 調べれば調べるほど、奥が深く“美術品”として大変貴重な作品ということがわかった。一つの作品を通して、歴史、伝承などに思いを馳せてみる。そんな時間があってもいいのではないだろうか。