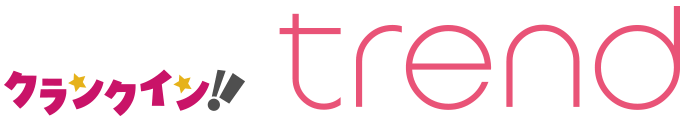『真田丸』で興味を持った人も注目! “城郭ライター”が教えるお城の楽しみ方

4月6日は“城(しろ)の日”。映画『信長協奏曲』や大河ドラマ『真田丸』など近年、歴史物の作品がヒットしている影響もあり、城目的で観光をする人が増えているという。歴女がブームになる前は、城が好きな人は男性が多いといったイメージがあったが、小学生の頃から城の魅力に惹かれていた萩原さちこさんは、“城郭ライター”の肩書きで全国各地の城を巡り、その魅力を書籍や講演、webなどで広く伝えている。目の付けどころが独特な萩原さん流の城の楽しみ方を教えてもらった。
【関連】城郭ライター・萩原さんもオススメする現存12天守<フォトギャラリー>
最初に城に魅せられたのは小学2年生の時。「家族旅行で松本城に行ったのがきっかけでした。天守の中の階段が梯子のように急なんですけど、『なんでこんなに昇りにくそうなんだろう』と思っていたら、母から『敵が攻めてきた時昇りにくくするためだよ』と聞いて感動して。ほかにもいろいろ工夫がされているのがわかって興味がわきました」という。女性は戦国武将から興味を抱く人も多いようだが、「私は軍事面から入りました。その作りから見える理にかなった先人の知恵にビビッときて…」と微笑む。
それからいろんな城を見に行くようになり違いを発見してさらに面白さを感じたという。「天守の形や装飾も違いますし軍事的な装置も違う。その違いにもちゃんと理由があるということで興味がわいてきて…」。外観も地域の気候によって変われば、時代によって作り方のトレンドも変遷しているという。「重要な場所にはおのずと立派な城が築かれますし、技術力や財力、作り手のセンスによっても違います」と説明する。
技術の継承が窺えることに気付くのも醍醐味だという。「北条氏がよく作っていた障子堀というものを、秀吉が後に大坂城で作っているんですね。秀吉は北条を滅亡させるにあたり北条の城を攻めていますから『これは使える』と技術を盗んだのではないでしょうか。また武田信玄・勝頼父子と激しい争奪戦をした家康の城を見ていくと、どうやら武田の技術を取り入れたようで、同じ地域でも最初に手を入れた城と後に改修した城ではつくりが違っています。秀でた築城術は受け継がれていくものなんですね」と話し、歴史好きにとっては興味深い話だ。
この記事の写真を見る
関連情報
-

X
-

Instagram