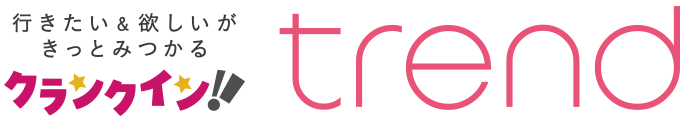90年代描く『ボクたちはみんな大人になれなかった』が2021年にも爆刺さりする理由
■描かれるのは時代のB面で生きる人たち
『ボクたちは大人になれなかった』は、世紀末の東京が緻密に描かれているものの、ブルセラ女子高生もアムラーも登場しない。シャ乱Qの「シングルベッド」を歌う人もいなければ、Mr.Childrenの「Tomorrow never knows」に涙する若者も出てこない。佐藤はテレビ業界で働いているのに『愛していると言ってくれ』も『ダウンタウンのごっつええ感じ』にも関わっていないし、下請け会社でよくわからない番組のテロップをもくもくと作っている。
森義仁監督は製作にあたって、かおりに似ている複数人にヒアリングをし、時代描写のディティールにこだわったという。劇中でフィーチャーされる小沢健二の楽曲は、代表曲の「ラブリー」や「ぼくらが旅に出る理由」ではなく「天使たちのシーン」だ。これは「かおり風の女性」のヒアリングによって、導き出された答えなのだという。
90年代を描いているのに、時代の象徴や代表曲は思いのほか出てこない。『ボクたちはみんな大人になれなかった』で描かれるのは、時代のB面で生きる“取るに足らない存在”たちの思い出だ。
原作には「ダサいことを何よりも許せない人で、前衛すぎるイベントによくふたりで出掛けた。チラシとポスターがオシャレなクソ映画、チラシとポスターがオシャレなクソ演劇に、よくふたりで足を運んだ」と書かれている佐藤とかおりは、クリエイターになるわけでもなく、カルチャー色の強い仕事をするわけでもなく、あくまで受け手として社会の隅で生きている。二人は時代の強者でも弱者でもない。普通の物語では描かれない存在だ。
「B面を生きる人たちの、取るに足らない物語」。だからこそ、よりリアルな90年代の描写が可能になっているのだろう。
これだけ固有名詞を書いてしまうと「サブカル映画なんだろう」と思ってしまうかもしれない。でも『ボクたちはみんな大人になれなかった』は、単なる懐古主義のサブカル映画になりさがらず、見る者に深く突き刺さる。森監督は公式Podcastで、本作について「時代のジュークボックスにしたくなかった」「あまりに自分ごと化してしまう物語」と語っており、サブカルワードに霞まない普遍性が漂う構成になっている。
筆者である私自身、雑誌を見て文通相手を探したこともなければ、六本木のWAVEという場所にも行ったことがない。でも『ボクたちはみんな大人になれなかった』は、どうしても自分を投影せずにはいられない。当時の空気感を知らなくても、スクリーンの中に生きる佐藤は「イタい20代の私」に見えてしまう。他人事とは思えない物語に、心臓をギュッと掴まれる124分なのだ。
次ページ:イタいあの頃は、恥ずかしくもあり、愛おしくもある