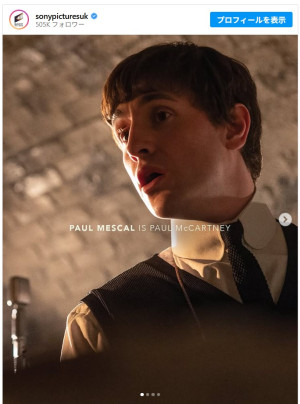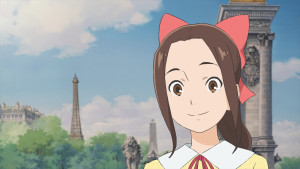『ゴジラ』1954年の第1作を見てみたら…“戦後たった9年後”の生々しさに満ちていた!
■ “戦後たった9年後”を感じさせる生々しいセリフ
前述したように、『ゴジラ』は怪獣映画であるが、一方で人間ドラマでもある。『ゴジラ』第1作を見ていて、ハッとしたのは下記の会話だった。
電車内にて。ゴジラの出現を伝える新聞を広げる男女3人の乗客が以下のような会話を繰り広げる。「やーね。原子マグロだ放射雨だ。その上今度はゴジラと来たわ。東京湾にでもあがりこんできたらどうなるの」「まず真っ先に君なんか狙われる口だね」「嫌なこった。せっかく長崎の原爆から命拾いしてきた大切な体なんだもの」「そろそろ疎開先でも探すとするかな」「私のもどっか探しておいてよ」「あーあ、また疎開か。全く嫌だなあ…」。
「長崎の原爆から命拾いしてきた」「また疎開か」といったセリフは、本作が終戦からわずか9年後に作られたものであることを強烈に印象づける。最新作『ゴジラ-1.0』も戦後をVFXの技術で忠実に再現していた。しかし、こうしたセリフには、「戦後直後」のリアリティをまた別の形で感じさせてくれる。
■ オッペンハイマーに重なる“創造者”の苦悩
ついにゴジラが東京に上陸。防衛隊による重火器での攻撃や、高圧電流で感電死させる作戦も不発に終わり、東京は焦土と帰す。
ゴジラの再上陸が恐れられる中、宝田明演じる主人公らは、芹沢博士が発明した酸素破壊剤「オキシジェン・デストロイヤー」をゴジラに対して使用させてほしいと博士のもとに直談判に訪れる。「オキシジェン・デストロイヤー」は、水中の酸素を一瞬のうちに破壊し尽くしあらゆる生物を窒息死させるという恐るべき兵器だった。
平田昭彦演じる芹沢は「オキシジェン・デストロイヤー」が「原水爆に匹敵する恐るべき破壊兵器」であるとし、一度使ってその存在が世界に知られれば、各国の為政者に悪用されかねないとこれを拒否する。その後、苦しんでいる被災者を目の当たりにして考えを変えた芹沢は、「1回限り」という約束で兵器を使用を許可。自らの生み出した兵器で見事ゴジラを倒すと、そのまま海底へと消えていく。自らが作り出した破壊兵器の秘密とともに…。
途方もない兵器とそれを生み出してしまった創造者の苦悩といえば、クリストファー・ノーラン監督による伝記映画でも話題の「原爆の父」ロバート・オッペンハイマーにも重なる。『ゴジラ』第1作は単なる特撮映画ではなかった。第1作にして、すでにゴジラの出現を通して人間とその愚かさ、苦悩に光を当てていた。だからこそここまで長きに渡って愛されるシリーズになったのではないか。(文・前田祐介)