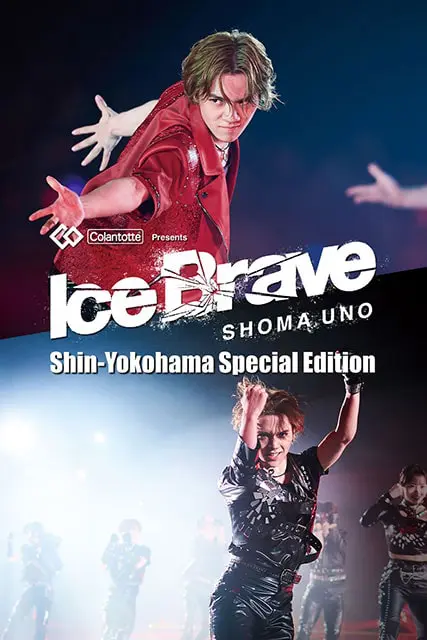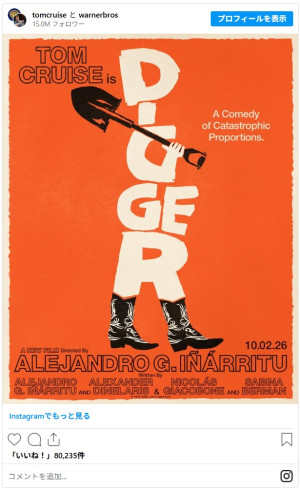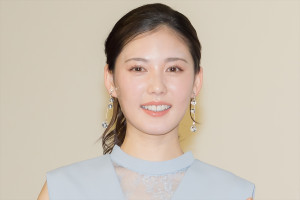「私は無価値だった」自身の人生を投影した女性像が胸に迫る 忘れられた傑作『WANDA/ワンダ』

世界中の映画人たちから「忘れられた小さな傑作」と賛美されながらも、長い間観ることの出来ない伝説的作品だった、監督・脚本・主演のバーバラ・ローデンのデビュー作にして遺作となった映画『ワンダ』(1970)が、今夏日本で初公開される。虐待を受けていた子ども時代から逃れ、16歳で故郷を離れてサバイバルしてきたひとりの女性が、自身の人生を投影して作り上げたアメリカ・インディペンデント映画の代表作だ。
【写真】アメリカの底辺をさまよう女性を切実に描く『WANDA/ワンダ』場面写真
主人公は、ペンシルベニア州の田舎に住む、いつも何かを諦めたような表情をしている女性ワンダ。妻や母としての役割を果たせず夫に離別され、職にもつけず、わずかな有り金もすられて一文無しになってしまう。すべてを失った彼女は、薄暗いバーで知り合った傲慢な小悪党の男と、いつの間にか犯罪の共犯者として逃避行を重ねることに…。
主人公ワンダはかなり風変わりな女性。育児放棄で夫に離婚訴訟を起こされ、法廷になんと頭にカーラーを巻いたままの姿で現れ、あっさりと離婚を受け入れる。そして、ビールとその日の寝床を提供してくれる男を吸い寄せながら渡り歩く。男を手玉にとる悪女でもなければ、無垢な犠牲者でもない。悲惨な境遇の自分を恥じたり責めたりもしない。映画でよく描かれる貧しい女性の定型パターンを軽々と飛び越え、時に無様な姿をさらしながら本能的に生きていく。この観る者に“媚びない”ヒロイン像にあっけにとられてしまうと同時に、何故かどんどん惹きつけられてしまう。
その一方でストーリーもきちんと緩急があり、彼女の苦しみや自己評価の低さが垣間見え、心を動かされる場面やセリフがある。男の犯罪計画に渋々加担していたワンダが、窮地に陥った男をとっさに助けるシーン。男に「良くやった」と感謝され、それまでほとんど笑顔を見せなかった彼女が、まるで親に褒められた子どものように無邪気な笑顔を浮かべる。おそらくこれまでの人生で褒められたり認められたりすることなどほとんどなかったであろう彼女の、この嬉しそうな表情は胸に迫るものがある。
監督・脚本・主演のバーバラ・ローデンは、1932年にアメリカ・ノースカロライナ州で生まれた。幼少期に両親が離婚し祖父母に育てられ、16歳でニューヨークに移住。ロマンス雑誌のモデルとして働き始め、後にアクターズ・スタジオで演技を学び女優として活動する。1966年に『エデンの東』『波止場』の巨匠監督で23歳年上のエリア・カザンと2度目の結婚。1970年にわずかな予算で自ら監督・脚本・主演した『ワンダ』を制作した。
『ワンダ』は1970年のヴェネツィア国際映画祭最優秀外国映画賞を受賞、1971年のカンヌ映画祭でも唯一のアメリカ映画として上映され国際的に高い評価を得たが、本国アメリカではニューヨークの映画館1館のみで1週間上映された後、人々の記憶から忘れ去られた。ローデンは本作の製作後、長編映画を監督することはなく、1980年に48歳で病死している。
ローデンは生前こう語っている。「私は無価値だった。私には友達がいなかった。才能もない。私は影のような存在でした。学校では何一つ学ばなかった。子どもの頃は映画が嫌いだった。スクリーンの中の人々は完璧で、劣等感を抱かせた。私は自分の世界に閉じこもるように、自分には何の価値もないと確信して人生を過ごしてきました。自分が何を望んでいるのか分からないが、何を望んでいないのかは分かっている。『ワンダ』を作るまで、私は自分が誰なのか、自分が何をすべきなのか、まったく分からなかったのです」「貧しい家庭で育った私もワンダのようになっていたかもしれない。彼女のような人は何百万人もいるのです」。
近年貴重な作品として認識され、2017年にアメリカ国立フィルム登録簿に永久保存登録された、この「アメリカの底辺社会の片隅に取り残された、崖っぷちを彷徨う女の物語」を、日本初公開となる今夏ぜひ目撃して欲しい。(文・古川祐子)
映画『WANDA/ワンダ』は全国順次公開中。