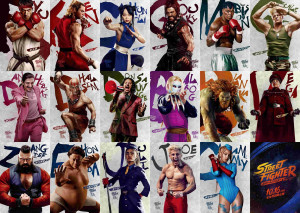山田裕貴、満たされない“ジョーカー”に共感 「ずっと乾いた状態」

2019年に公開され、世界を震撼させた映画『ジョーカー』。社会から爪はじきにされた孤独な男のタガが外れ、狂気の道化=ジョーカーになっていくさまをソリッドに描き、第76回ヴェネチア国際映画祭金獅子賞、第92回アカデミー賞主演男優賞&作曲賞を受賞。その“続編”となる『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』が11日に劇場公開される。そして本作の日本語吹き替え版声優に抜てきされたのが、俳優の山田裕貴だ。劇中ではジョーカーを追い詰めるハービー検事にふんしているが、本人はジョーカーに共感する部分も多いという。作品の魅力やジョーカー役のホアキン・フェニックスの怪演、さらには自身が抱える“苦悩”について――。表現者としての本音を語ってもらった。
【動画】真剣なトーンで『ジョーカー2』を分析する山田裕貴
■俳優目線で“ジョーカー”を分析
――山田さんは雑誌の企画でジョーカーメイクをご自身で行い、2020年放送の『情熱大陸』では「新時代の怪優」と紹介されていましたね。怪優といえば、ジョーカーを演じる役者の絶対条件かと思います。
山田裕貴(以下、山田):そうでしたね。紹介をしていただけた時はとてもうれしくて、その呼び名に見合うようにならなければと思ったことを覚えています。
前々からジョーカーというキャラクターを演じてきた人たちは「役に入り込む方が多い」とは聞いていました。ホアキン・フェニックスさんに取材したというワーナー・ブラザースの方も「まだ役が抜けていなくて、ジョーカーなのかホアキンなのか分からなかった」とおっしゃっていました。それくらい没入できる役柄というのもあるでしょうし、おっしゃる通りどれだけ入り込めるかが肝でしょうから「怪優」や「怪演」と呼ばれるのでしょうね。僕自身、彼らの芝居を見て感じるものはたくさんあります。『ダークナイト』のヒース・レジャーさんの場合は歩き方や表情が独特でしたが、ホアキンさん版のジョーカーはよりドキュメントに近い、リアルなイメージを抱きました。無理に作っているわけではなく、本物の時間を感じさせるといいますか、もちろんお芝居ではありますが「この人は本当に生きている」という感覚を強く受けました。
――山田さんがお芝居をされる際は、作品や役によって「これは没入が必要だ」と選択して臨まれるのでしょうか。
山田:自分とはかけ離れている役柄もあるため、毎回それができればすごくいいなとは思います。僕の場合、意外と明るい役のほうが難しいということもあります。
――なるほど。テンションを上げないといけない大変さがあるのですね。
山田:そうなんです。逆に、自分のあまり見せない部分を解放するような役柄の方が、入り込みやすくはあります。ドラマ『ホームルーム』や『先生を消す方程式。』はジョーカーをイメージしながら演じたこともあり、すごく入り込めました。
――ハービー・デント役は、同じ吹き替えと言えど『Ultraman: Rising』とはまるで違ったものだったのではないでしょうか。
山田:『Ultraman: Rising』はCGアニメーションだったので、実写の吹き替えに挑戦するのは今回が初めてでした。こちらとしてはお芝居をされている俳優さんの声のトーンに合わせようとしてしまいますが、声を張って出した方が「ニュアンスが出ているからOK」と言われることが多くて。自然にしゃべればしゃべるほど抑揚がなくなりニュアンスが失われてしまうので、そのバランスを取るのはとても難しかったです。
――非常によく分かります。吹き替えにはリアル芝居とはまた別の正解がありますよね。独特の文化といいますか、お客さんの中に「このゾーンこそ吹き替え」というものがある気がします。
山田:音量にしろトーンにしろ本来であればリアルに沿った感覚でセリフを言いたい自分はいますが、マイクに乗せると「何か違う」となってしまって。それがゴールだと思いつつも、これまでの癖で違和感を覚えてしまう自分がいて、なかなか大変でした。
――山田さんは以前『東京リベンジャーズ』でのドラケン役の影響が大きいからこそ、イメージが付きまとうことへの葛藤もあるとおっしゃっていましたよね。はたから見ていると、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』で実写吹き替えに挑戦されて、ますます活動領域が広がってきた印象ですが、こうした葛藤の部分についてはいかがでしょう。