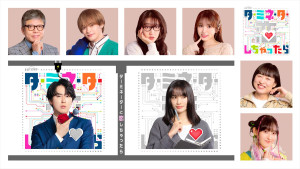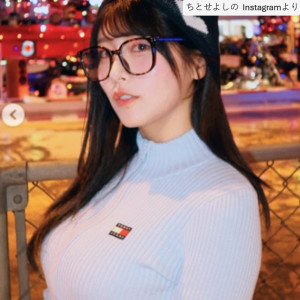木村達成、大河ドラマ&日曜劇場と躍進続く ストレートプレイ初挑戦から5年で得た気づきとは?

ミュージカル、ストレートプレイ問わずさまざまな舞台作品で主演を務め、近年は大河ドラマ『光る君へ』、日曜劇場『キャスター』など映像作品での活躍も目覚ましい俳優の木村達成。まもなく幕を開ける舞台『狂人なおもて往生をとぐ~昔、僕達は愛した~』では、主演として新境地に挑む。稽古真っ只中の木村に話を聞くと、30代を迎え俳優としてさらなる進化を遂げる今の心境が伝わってくるインタビューとなった。
【写真】木村達成、30代大人の男の色気あふれる!撮りおろしショット
◆タイトルの「狂人」が心に刺さった
本作は、劇作家・清水邦夫が、1969年に安部公房の推薦で俳優座公演のために書き下ろした作品で、ある娼家に集まったさまざまな事情を抱えた男女が紡ぐ“家族ゲーム”を描く。第30回読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞した稲葉賀恵が演出を務め、女主人のヒモで、ここから逃げようとしているが彼女の優しさから逃れられない青年・出を木村が演じる。共演に岡本玲、酒井大成、伊勢志摩、堀部圭亮、橘花梨ら存在感あふれる顔ぶれがそろい、作品を彩る。
ピンクの照明が妖しげに光る娼家。大学教授と名乗る初老の男「善一郎」はここの女主人「はな」の客である。そして青年「出」は女主人のヒモで、ここから逃げようとしているが、彼女の優しさから逃れられない。この娼家には若い娼婦「愛子」もいて、彼女の客である若い男「敬二」もやって来る。
やがて彼ら5人はまるでここが一つの家族であるかのようなゲームを始める。初老の男が父親、女主人が母親、ヒモの青年が長男、若い娼婦が長女、その若い客の男が次男。ところがその家族ゲームとは…。
 舞台『狂人なおもて往生をとぐ~昔、僕達は愛した~』公演ビジュアル
舞台『狂人なおもて往生をとぐ~昔、僕達は愛した~』公演ビジュアル
――本作のオファーをお聞きになった時の心境はいかがでしたか?
木村:清水邦夫さんの作品を深く知らず、この作品がどれだけの破壊力を持っているのか理解していなかったのですが、まずタイトルが刺さりました。本を読んでみると、どこをどう切り取って狂人と言っているのか気になるところがあったので、ぜひやってみたいなという気持ちになりました。
――タイトルのどんなところが刺さったのでしょうか?
木村:やっぱり「狂人なおもて」というところですね、「狂人でさえも往生をとげることができる」 (注:親鸞の言葉に「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」とある)。何をもって狂人と言われているんだろうと。この世界観は、蓋を開けて見ても何をどう切り取って狂人と言っているのか、またどんどん分からなくなってきているところもあります。
――演じられる出はどんなキャラクターと捉えていますか?
木村:端的に説明しづらいんですよね。1939年に生まれて、戦前と戦後に挟まれている男で、親が大学の教授。親は戦前の教育を続けたほうがいいと言っている中、世の中では道徳教育を推奨している。そこでもまた間に挟まれている。だからこそ学生運動に立ち上がったり…。
かわいそうな奴です。この時代に生まれてかわいそう、そんな感覚ですかね。

――出に共感する部分はありますか?
木村:うーん。僕は今の時代に生まれたことを間違えたとは思ってないし、生まれた環境でガタガタ言いたくないから、今出せる100%みたいな生き方をしているつもりなんですけど、でもこれって、環境が整っているから言えることなのかなと思うこともありますし…。
稽古をやっていく中で、「若者よ、立ち上がれ!」というようなメッセージ性を作品の裏テーマとして感じてしまっている分、刺さったというんですか。出も30歳の設定なので、すごく刺さる部分があったのかなって稽古を通して感じています。
――30代になると、今までとは違う、今まで通りではいられないという考えになることも多いですもんね。
木村:もう子どもじゃないとかね。自立していかなきゃいけないっていう芽生えはどこかである中、この娼家の閉鎖的な空間が、閉鎖的な日本の象徴として作っているような感覚があるので。ここから抜け出したい、新たな変化を求めて外に出ていこうと奮い立つ、出の脱出ゲームみたいな感じでやっています。
――上演決定のリリースで「今回は自分が何度ぶっ壊れるか、楽しみです(笑)」とコメントされていました。
木村:ぶっ壊れてないです、まだ(笑)。“ぶっ壊れる”っていう表現に“ガムシャラになる”っていうことも含めたら、もちろんガムシャラにはやっていますけど、ただ単に出たとこ勝負で頑張っているわけではなく、本当に脳みそをフル回転で使って、舞台上を広くそして人との関係を強く持とうと考えた時の力の使い方みたいなものが、出っぽさにつながって来ている分ぶっ壊れはしてないというか。そこらへんは上手いこと行ってるなと感じています。