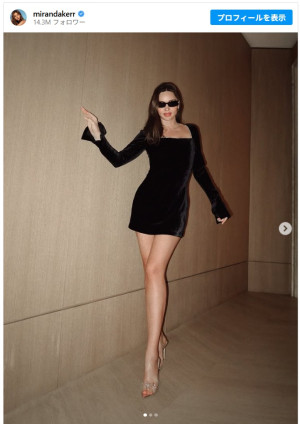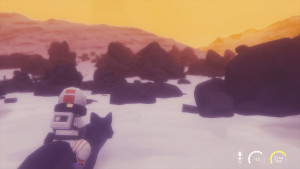佐藤二朗、パブリックイメージとは真逆の監督作――“二朗さんって本当はどういう人?”

俳優の佐藤二朗が主宰する演劇ユニット「ちからわざ」で2009年に初演された舞台劇を、佐藤自らが監督・脚本を務め映画化した『はるヲうるひと』。その作風は、コメディー映画で日本中に笑いを振りまく彼のパブリックイメージとはまるで真逆。山田孝之演じる不幸の極地でもがき苦しむ主人公・得太の姿を目の当たりにすると、俄然、“佐藤二朗”の頭の中が気になってくる。いつものお茶目な二朗さんは仮の姿か、それとも笑いとシリアスをつなぐ何かがあるのか。そんなことを短絡的に勘ぐっている時点で佐藤監督の罠にハマっているような気もするが、本人に直接、思いをぶつけてみた。
【写真】ダークな役柄もハマる佐藤二朗 インタビューフォト
舞台は、置屋が点在する架空の島。“春を売る”女たちに囲まれながら、寄り添うように暮らす青年・得太(山田)と虚弱な妹・いぶき(仲里依紗)は、置屋を経営する義兄・哲雄(佐藤)の暴君ぶりに怯えながら、歯を食いしばって生きていた。だが、ある日、彼らを混乱させる家族の衝撃の真実が発覚する…。山田、仲、佐藤の壮絶な愛憎劇に振り回されながら、自らも悲惨な人生を背負う女たちを坂井真紀、今藤洋子、笹野鈴々音、駒林怜らが熱演する。
 映画『はるヲうるひと』より (C) 2020「はるヲうるひと」製作委員会
映画『はるヲうるひと』より (C) 2020「はるヲうるひと」製作委員会
■映画を観た人から聞かれる「二朗さんって本当はどういう人?」
佐藤にとって長編映画監督第2作となる本作。実は、初メガホンをとった前作『memo』(2008)でプロデューサーを務めた永森裕二と、かなり前から2作目の構想を練っていたという。「新たにオリジナル脚本を書いたり、ミーティングをしたり、いろいろ方向性を模索していたんですが、なかなか話が進展しなくて…。そんなある日、『はるヲうるひと』の舞台を観ていた永森さんから、『あれを映画化したらいいんじゃない?』という助言があって、そこから監督2作目のプロジェクトが一気に動き出した感じですね」。

永森の狙いは定かではないが、「彼はプロデューサーですから、僕のパブリックイメージの裏側を突ける、という思いがあったかもしれませんね」と推測する佐藤。彼自身も、「カウンターというか、僕の中にも『世間のイメージを少し裏切ってやろう』という思いはあった」と本音を吐露。ただ、「それは映画を観ていただくためのサブ的な意味で、メインは、あくまでも自分のやりたいことを本気で表現すること。全力でやり切るという点では、僕にとって、本作も、『勇者ヨシヒコ』の仏(ほとけ)も同じこと。そこには区別はないんです」と力を込める。
『勇者ヨシヒコ』の仏と同じ…それはつまり、どういうことなのか。「この舞台を観た方や映画の試写を観た記者さんから、『二朗さんって本当はどういう人?』ってよく聞かれるんですが、そもそも、この題材は、僕が抱えている心の闇とか、本当の自分を露呈するとか、そういうことではないんですね。確かに『勇者ヨシヒコ』とはまったく毛色の違う作品ではありますが、一人の俳優として、監督として、この題材で作品を撮ってみたい、そしてやるからにはとことん“たのしみたい”。それは“楽”じゃなくて、“愉”かもしれませんが、コメディーもシリアスも同じ地平にあるものとして捉えているだけなんです」。
 映画『はるヲうるひと』より (C) 2020「はるヲうるひと」製作委員会
映画『はるヲうるひと』より (C) 2020「はるヲうるひと」製作委員会
ある親しい監督から、「二朗さんの芝居には怖さがある」と言われたことがあるという佐藤。「女優さんと面白い(あるいは逆にシリアスな)セリフのやりとりをしていても、『二朗さんは絶対どこかで崩れる』という“危うさ”があるらしいんですね。それはもしかすると、僕が『コメディーとシリアスを分ける必要はない』と思っていることが影響しているかもしれません」と思いをめぐらす。「ここからここまでが笑いで、ここからここまでシリアスっていう線引きはナンセンス。笑っていたらいつの間にか泣いていたとか、泣いていたらいつの間にか笑っていたとか、そういうところに僕は魅力を感じるんです」。