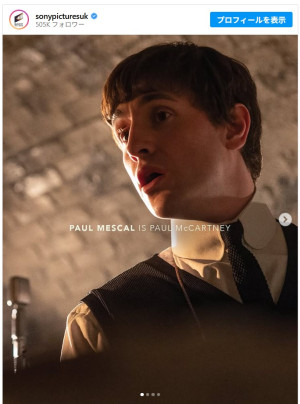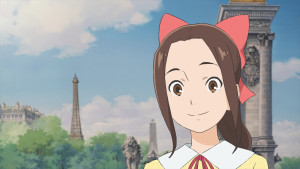『M-1グランプリ』2001年の第1回を見てみたら…松本人志ら「審査員」は実は優しかった

どんなにヒットし、どんなに長く続いたシリーズにも必ず「第1回」が存在する。長く続いたシリーズであればあるほど、紆余曲折を経て今の姿があるはず。長い歴史をまだ知らない第1回は、いったいどんな形でスタートを切ったのか? 知られざる第1回を振り返る「第1回はこうだった」。今回は2001年に開催された漫才の頂上決戦『M-1グランプリ』(ABC・テレビ朝日系、以下『M-1』)第1回大会をプレイバック!
【写真】13年ぶりの女性コンビも進出! 『M-1グランプリ2022』ファイナリストはこの9組
今年の開催で18回目を迎える『M-1』は、「漫才に恩返しをしたい」という島田紳助さん(2011年に芸能界引退)の意思のもと創設された日本一の漫才師を決める漫才コンテスト。2011~2014年の中断を経て、毎年年末に生放送されている。優勝者には賞金1000万円が授与され、その日を境に文字通り芸人人生が変わる。今や年末の国民的行事へと成長しており、今年は史上最多の7261組がエントリーし、来週18日に決勝が放送される。そんな『M-1』の第1回大会はどうだったのか?
■ 何から何まで手探り状態!
第1回とあって、番組の段取りも、出場者も審査員もみな手探り状態だったのが興味深い。『M-1』といえば、のちには輝く大きな「M」の字が印象的な豪華な舞台セットがトレードマークだが、それに比べると第1回はお世辞にも豪華とは言えない灰色を基調とした地味なセットで繰り広げられた。
近年は「笑神籤(えみくじ)」というくじが用いられ、その場で出番が決まる『M-1』。出場者は自身のネタ披露まで控え室で待機する流れが定着しているが、第1回では出場者全員がまず壇上に呼ばれ、出番順のくじを引かされる。まだ若手のフットボールアワーやチュートリアル、デビューしたばかりのキングコングらが少し緊張した固い表情を浮かべて整列する姿がほほ笑ましい。
審査員も同様で、おっかなびっくりの審査だった模様。すでにこの当時、”笑いのカリスマ”の名をほしいままにしていた松本人志も、こうした賞レースの審査員を務めることはこの時がほぼ初めて。いよいよネタ披露が始まる前には、先輩・紳助さんに「どんなテンションで行きます?」と困惑ぎみに問いかける一幕もあった。
当時は関西地区の視聴者でもなければ、視聴者にとって漫才を見る機会はお正月の特番ぐらい。お世辞にも漫才シーンが盛り上がっているとは言い難い状況だった。そんな状況の中、突如1000万円の賞金を懸けた大きなコンテストがゴールデンタイムの全国放送に誕生したのだから、無理もないのかもしれない。
そのほか、今では司会は今田耕司と上戸彩のコンビがおなじみだが、第1回の司会は紳助さんと共に人気ラジオDJの赤坂泰彦と”東大卒女優”として活躍していた菊川怜が担当。特に赤坂は、慣れないお笑い賞レースの司会ということもあってか、出場者の中川家を「石川家」、ハリガネロックを「アメリカンロック」と立て続けに言い間違え、会場で爆笑が起きるハプニングもあった。