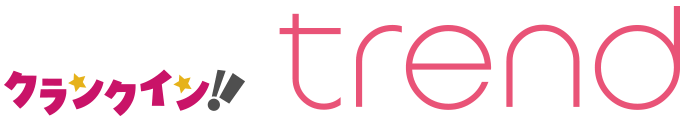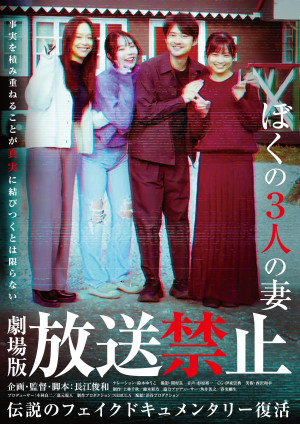夏が来れば思い出す――昭和の“怖い話” 呪物に怪人、心霊スポットも
今は日本全国、津々浦々の心霊スポットを検索一発でチェック可能だが、昭和の時代は各地にマイナーな穴場が数多く存在。筆者の地元では国道246号線の伊勢原市と秦野市を結ぶ善波峠にある奇妙な看板が有名だった。
小さな看板に並ぶ文字は「もう死なないで、準一」。夜になるとぼんやり白く明かりが灯り、寂しい峠道の暗がりにポツンと看板が浮かび上がるのが何とも恐ろしかった。かつて、付近の山道で17歳の少年がバイクで事故死。その幽霊が走行中の車の前に現れるので、何度も死なないで欲しいと願いを込めて両親が設置したという。あるいは、この場所で事故が相次ぎ、亡くなった人はそろって「準一」という名前だったとも聞いた。
実際には、無事故の祈りを被害者の名で掲げた文面が誤解を生んだわけだが、この準一くんが自分の親と親しかったと知ったのは最近のこと。母親が「準ちゃん」と呼んで話すので、怪異の詳細を聞こうとしたら口をつぐんでしまった。彼らにとって準ちゃんは怖ろしい幽霊ではなく、今も記憶のなかで生き続ける青年なのだ。
 ※画像はイメージ
※画像はイメージ
この一件でふと、蘇った記憶がある。小学校の修学旅行で訪れた日光の華厳の滝で、心霊写真を撮った友達のことだ。オカルトっ子のバイブル、中岡俊哉著の『恐怖の心霊写真集』を愛読していた筆者は、その友達が宝くじを引き当てたように思えて悔しかった。
しかし、暫くして彼は写真を封印した。親しい間柄だったので、見せてくれと頼んだら渋い顔をされた。どうにか口説き落として写真を手にすると、滝の風景に大きく女性の顔が浮かんでいる。ヤラセや錯覚の余地などない「本物」だった。言葉をなくしていると、彼は苦々しく「これは処分する」と写真を持ち去った。本当に不気味なものは世の中には出回らず、ひっそりと個人の胸に葬られている。そう実感した出来事だった。
思い返せば、昭和の怪談は最新鋭の機器や最先端の場所で、常識では考えられない怪異が起こる話が多かった。一方、平成以降の怪談、例えば「杉沢村」は村民皆殺しで消滅した異界村の話だが、場所は特定できず、検証の術もない。その肝は封印された遠い過去にあり、昭和とそれ以降の時代の間には大きく深い溝を感じる。
また、昭和の怪談は家族や知人、タレントや有名人ら、顔の分かる相手が発信源だった。対して、ネットの怪談は「恐さ」こそ共有できるが、相手の顔は見えない。ただ、住環境や生活習慣が大きく変化しても、怪談は思い込みや勘違いと背中合わせに存在する。不穏な光景を前に、怪しい物語を連想する想像力がある以上、恐怖の扉は常に開かれる時を待っているのだ。
(文:山崎圭司)