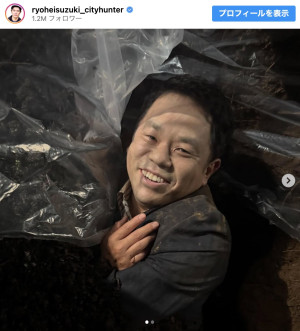木村拓哉「そんなんじゃOK出さねえよ」と言われた 自身にとっての“教官”の存在を明かす

2020年のスペシャルドラマ放送以来、警察学校を舞台に「どんな些細な嘘も見抜く」鬼教官・風間公親と生徒たちの真剣勝負を描いてきた「教場」シリーズ。2026年、ついにその集大成となる2部作が公開される。前編『教場 Reunion』は現在Netflixで配信中、後編『教場 Requiem』は2月20日より劇場公開となる。そこで、主演の木村拓哉にインタビューを実施。多数の若手俳優と共演する「教場」での木村は、これまでのイメージを覆す「引き算の演技」で高い評価を受けてきたが、「本人的には掛け算」だと笑う。若手を育てる意識があるのかと問えば「現場は養殖場じゃない」と一蹴。その言葉の真意とは?
【写真】目線をそらした姿もかっこいい! 木村拓哉、撮り下ろしフォト(3枚)
■過去シリーズと「比べる」のは「甘え」――初めて芽生えた感覚
――人気シリーズとなった「教場」ですが、改めてその魅力、面白さはどこにあると感じますか。
木村拓哉(以下、木村):作る面白さはやっぱり「異質」であることですね。今のご時世とは逆行しているような内容でもありますし。チープな例えかもしれないですけど、激辛好きの人たちが楽しむエンターテイメントというか、“味”は激辛に近いのかなって。「本当によくみんなそれ、最後まで食べきるね」っていう思いに近い気がします(笑)。
――その“味”は現場でどのように作られていくのでしょうか。
木村:実際に味を作るのは現場ですね。「これぐらいかな」という分量で、現場で実際にやってみて、共演者の方があっての辛さなので、最終的には現場でセッションして味が決まっていく形です。
――今回は、綱啓永さん、齊藤京子さん、倉悠貴さん、佐藤勝利さん、猪狩蒼弥さん、中村蒼さんなどが「205期生」の教え子たちとして登場します。俳優さんたちとのお芝居で新鮮に感じられたことはありますか。
木村:第1作からやらせていただいているという事実がある中で、自分含め現場のスタッフ、もちろん監督も、つい「比べる」という甘えに走りたくなる瞬間があるんです。「前の奴らはもっと練習してたよ」などと言いたくなる。でも今回、それが「甘え」だと気づいたんです。
 映画『教場 Reunion』本ビジュアル (C)フジテレビジョン (C)長岡弘樹/小学館
映画『教場 Reunion』本ビジュアル (C)フジテレビジョン (C)長岡弘樹/小学館
――過去と比べるのは、制作・キャスト含めた常連メンバーの「甘え」だと?
木村:そうですね。だって、今この場で一緒に向き合ってくれている、一緒にセッションしている、一緒に構築している人たちが全ての答えであって。今一緒にやってくれている人が何をどうするか、それがもし監督の求めるものと違うならば、その場で「もっとこうして」などと具体的に伝えるべきなんだろうと思いました。その感覚になったのは今回が初めてかな。
――今回の撮影で特に印象に残っているのはどんなことですか。
木村:毎シーズン、同じ制服を着て同じ空間にいるんだけど、それぞれの向き合い方があるんだな、と。これもおじさん・おばさんの甘えだと思うけど、「○○世代」と一言で形容しがちじゃないですか。でも、表現者としては個の集合体で、舞台は警察学校で、フィクションの世界を構築する試みもあって。今まではそうした役者の個々の実態と、作品の世界観をつなぐアプローチが直角ぐらいで済んでいたところ、今回はその角度が開いたというか。距離自体が遠くなったわけではないんですけど、そこをつなぐためのナビゲートの仕方が変わったと感じました。
――ナビゲートの仕方はどんな風に変わったのでしょう。
木村:たとえば「止まれ」という標識があると、みんな規則として止まってくれる。でも、表現としては「『止まれ』でいいの? 『止まって』の方がいいの? 『止まってください』の方がいいの?」と、今の時代では一瞬、立ち止まって考えなきゃいけない。
――「今のご時世と逆行している」とおっしゃっていたのは、そうした「教場」という特殊な世界の中での人間関係や指導法などですね。
木村:全部アウトだよねって、よくスタッフと話しますよ(笑)。この世界観になじむまでは日常生活との大きな開きが気になる人もいるだろうけど、そこをゆっくりねじ伏せて違和感をなくしていくのが僕らの仕事ですよね。