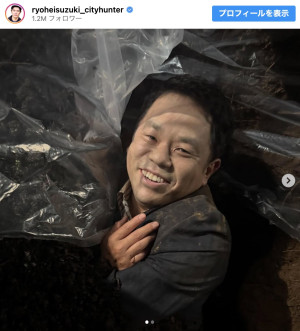木村拓哉「そんなんじゃOK出さねえよ」と言われた 自身にとっての“教官”の存在を明かす
――今の時代との違いがある一方で、視聴者にはすでに「教場」という世界観も、風間教官の人柄も浸透しています。最初は風間教官に何を考えているかわからない怖さ・不気味さも感じましたが、今は「実は優しく温かい人」と視聴者は知っています。そうした中で演じる難しさはありますか。
木村:演じる側としては、やりやすい・やりにくいは別にないですよ。毎回脚本の中ではいろんなタイミングでいろんなトラップが仕掛けられているので、そこにワクワクしてほしいし、風間教官の見え方というのも、そこまでセルフプロデュース的なことはしていないです。むしろ、セリフを「これ、どうする? 言わない? 言った方がいい?」という判断は、監督に委ねています。
――「教場」では、毎回さまざまな試練を乗り越えた教え子たちが卒業していきます。卒業式のシーンというのは、見送る側として感情の昂りがあるものですか。
木村:卒業式のシーンは、メインキャストの他に大勢の方が参加して撮影するので、まずはそれが大変で。「今からこの端から端まで、みなさん全員で一つの瞬間を作ります」というシーンでは、監督の求める画があって。でも、そこに集まっているのは、AIが生成したものでも何でもなく、本当に今その場にいる生身の人たちなんですよね。一人が一声を発した瞬間に、全員が全く同じタイミングで同じ姿勢を作るんですけど、「やってみよう」から始まり、テスト、本番の「よーい、スタート!」。そこで監督が「違うよ」と声がかかると、「これ、どう伝えればいいだろう」という緊張感が走ります。そんな中、「教場」で向き合ってきた約30名は他のみんなのお手本になってくれている。卒業式は、そんな彼らがいてくれることが誇らしいと感じる瞬間ですね。

――実際の学校の卒業式でよくある光景のように、「教場」でも卒業式の後、撮影現場で「お世話になりました」と教え子が言いに来るような交流はあるんですか。
木村:そうですね。今回も、自分自身がクランクアップする瞬間に、役衣装でもなく私服の状態の何人かが急に現れて、花束を渡してくれて。それは本当にありがたかったですね。
――木村さん自身にとって、「教官」のような指導者の存在はいらっしゃいましたか。
木村: もちろん。例えば僕が『若者のすべて』(フジテレビ/1994年)で、まだ俳優としてなんとなく演じていたとき、「いや、そんなんじゃOK出さねえよ」と言ったのが、この「教場」シリーズの中江功監督でしたし。彼が30歳で監督デビューした頃じゃないかな。他局では、(『華麗なる一族』の)福澤(克雄)さんや、今は亡き生野(慈朗)さん。映画の現場においても、『武士の一分』(2006年)に続いて今回また『TOKYOタクシー』でご一緒させていただいた山田洋次監督や、(『無限の住人』の)三池(崇史)さんももちろんそうですし。
――そうした方々から言われた言葉で、今も大切にしているものはありますか。
木村:言葉をいただいたときに「その答えって何だろう」と考えて、そこから自分なりの答えを出したけど、たぶん今後も考えていくだろうと思ったのは、山田監督からいただいた「心を脱いでください」ですね。
――「心を脱ぐ」とは?
木村:その時は前に進まなきゃいけないから、理解していないのに「はい」と言った自分がいたんですね。「心を脱ぐ」ということはどういうことなんだろう、多分こういうことなのかなとその時は思って本番をやらせていただいて、カットがかかって「いいでしょ」となったけど、正解だったのかどうかは分からない。でも、この視点は忘れちゃいけないかもなと思って、その後の自分のテーマの一つになっていますし、今回の「教場」でも探り続けています。