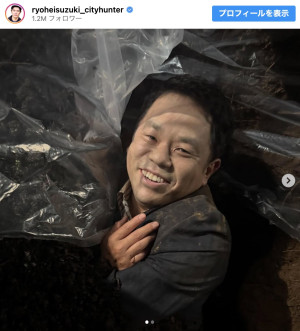木村拓哉「そんなんじゃOK出さねえよ」と言われた 自身にとっての“教官”の存在を明かす
――これまで数々の作品の真ん中で輝きを放ってきた木村さんが、「教場」シリーズでは若手を引き立てる「引き算の演技」で「新境地」とも評価されています。ご自身のキャリアにおいて何らかの心境の変化などあったのでしょうか。
木村:全然ないです。本人的には引き算というより、掛け算なんですけどね(笑)。というのは冗談にしても、それぞれの作品がどうか、「誰」を演じるかということであって、お話とキャラクターによってお芝居は当然変わるものですから。それに、「僕は中心じゃなきゃ嫌だ」なんて言うこともないし、そういうのが一番嫌いなタイプ(笑)。「真ん中で輝く」と言ってくださいましたが、それはある種不正解なのかもしれないですよ?(笑)。
――「教場」卒業生の若手俳優さんを取材したとき、木村さんはご自身の撮影がない時も現場にできるだけ足を運んでいらっしゃった、その「座長」としてのあり方に学んだというお話を聞きました。座長として、若手を育てようという思いもあるのでしょうか。
木村:それも不正解です(笑)。そういうふうに思ってくれるのはうれしいし、ありがたいし、良いほうに作用してくれれば良いなとは思いますけど、現場は“養殖場”じゃないから。現場では生産性を高めるためにいろんなものが意図的に作られ、使用される中で、いかに“天然”を感じていただけるかが、結局はOKテイクになっていると思うんですよ。特に中江監督はそうだと思います。

――若手に対しても「育成」という向き合い方ではない、と。
木村:一対一のシーンであれ、ステージであれ、それが若手だろうとベテランだろうと、向き合う相手に対して、自分の持ちうる100かそれ以上で常にぶつかるしかないので。それが相手を呑み込むような向き合い方なのか、逆に相手が距離を詰めてくるのを一切意に介さず、目も合わせずかわすだけなのかは、作品や役柄、シーンによって変わりますし、そういうやり取りがとても楽しいんですね。
――共演者の方々もそうした木村さんの向き合い方に対し、「挑む」というモチベーションで来るのでしょうか。
木村:そうした真剣な思いはひしひしと伝わってきますね。それを感じられた時は、こちらも、より「いざ!」と気合が入りますし、感じられないときには、こちらから「今から行くよ」と合図を出さないといけないかもしれない。それは自分からなのか、演出部の役目なのか、監督の役目なのか、TPOによって変わってくるかもしれないですけど。でも結局、今一緒に作品を作っている人たちが全ての答えです。ドラマの現場は、養殖場じゃなく、そこで生きている人・感情という“天然のもの”を捕まえにいく場所だから。
(取材・文:田幸和歌子 写真:松林満美)
映画『教場 Reunion』は、Netflixにて配信中。映画『教場 Requiem』は、2月20日より公開。