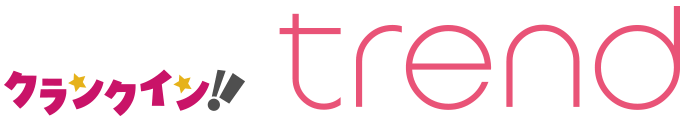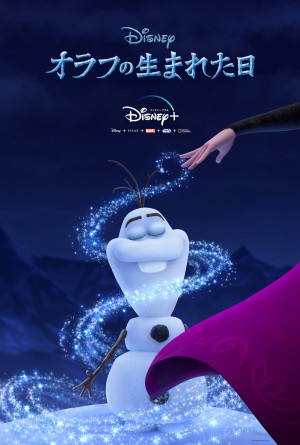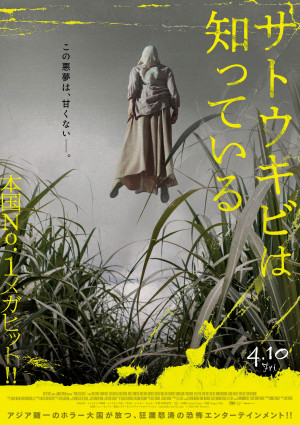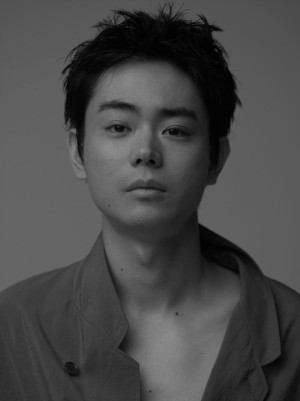『ウルフウォーカー』物語の根幹に迫る “エクスカリバー”でおなじみ「ケルト神話」とは

ケルト神話に着想を得たアニメ映画『ウルフウォーカー』が、10月30日より全国公開される。日本のアニメやゲームにも影響を与えるケルト文化とは、そもそもどのようなものだろうか?
『写真』ケルト神話を元に少女とオオカミの絆を描く 『ウルフウォーカー』場面写真(11点)
本作を製作したアニメーションスタジオ「カートゥーン・サルーン」は、これまでもアイルランドの歴史や神話を題材に、創造性あふれる作品世界を色彩豊かな2Dアニメーションで作り上げてきた。本作は、『ブレンダンとケルズの秘密』(2009)、『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』(2014)に続く、ケルト三部作の完結作品となる。
物語の舞台となるアイルランド・キルケニーには、眠ると精霊が体から抜け出してオオカミの姿になって大地をさまよい、人間の体は眠ったままになるという伝説があり、本作もそんなケルト神話に着想を得て制作が始まった。
そもそもケルトとは何なのか? 古代ギリシャ人が紀元前600年頃に西ヨーロッパに居住した異民族を「ケルトイ」と呼んだことで、現代でもケルトという名称が定着。ケルト人の起源はいまだ不明な点が多いが、彼らは多数の部族が共通の文化や言葉により結びついたとされている。
ケルトには、記録せず、語りと記憶力だけを真実とする習慣があり、自然崇拝と多神教が口承されてきた。「石」そのものへの信仰があったほか、自然とつながりのある妖精や巨人などもよく登場し、神々や英雄の物語は、王権に匹敵するほどの絶大な力を持っていた。しかし6世紀以降、修道士により古代の伝承譚が書き留められ、現在残る多くの神話や伝説が残されたと言われている。後年には伝来したキリスト教と融合することで、独自のキリスト教文化が生まれた。「輪廻(りんね)転生」の考えが形成されており、ケルトの神話や伝説では人間が動物に生まれ変わったり、神が英雄になったり、妖精が人間の子供を産んだりと、神、人間、妖精がめまぐるしく転生する。
本作の主人公ロビンが出会う少女メーヴも、人間とオオカミがひとつの体に共存し、魔法の力で傷を癒すヒーラーでもある“ウルフウォーカー”。オオカミを自分たちより強い生き物と捉え、尊敬の念をもって接した古代ケルトの人の信仰を元に、人と人ならざる者の対立と友情が描かれる。
ファンタジーでおなじみの妖精、ドラゴン、姫君や騎士、湖から現れる聖剣エクスカリバーなど、日本ではゲームやアニメの題材になることが多く、日本の神道の考え方と良く似ているとも言われているケルト伝説。ケルト文化や神話を調べてから映画を見るといっそう深く楽しむことができるはずだ。
アニメ映画『ウルフウォーカー』は、10月30日より全国公開。