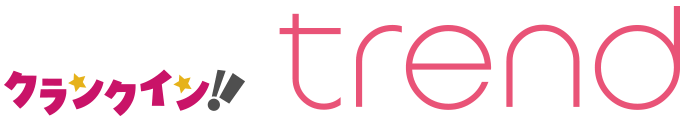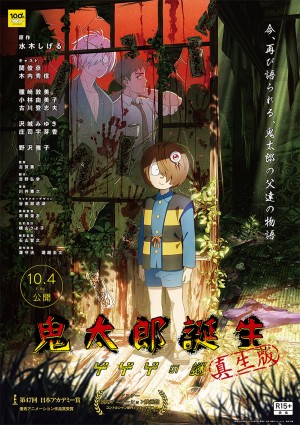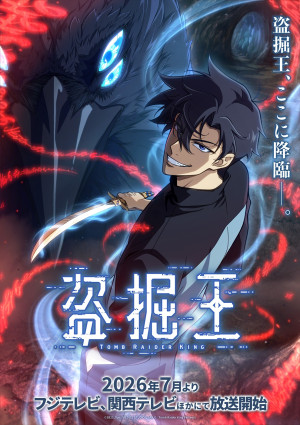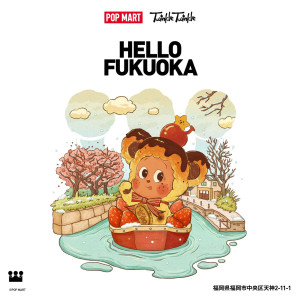映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』関俊彦&木内秀信、「鬼太郎の父は“人間は本来こうあるべき”という純粋な部分を持っている」
関連 :
――演じるにあたり、監督やスタッフの方からどんなディレクションがありましたか?
 映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』場面写真 (C)映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」製作委員会
映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』場面写真 (C)映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」製作委員会
関:今回は、昭和30年代の白黒日本映画のテイストでやりたいと言われました。僕は当時の白黒映画での役者さんの喋りって、みんな早口という印象があって。
木内:僕もオーディションのときに、「白黒映画のような雰囲気を出したいので、ちょっと早口でハキハキ喋って欲しい」というディレクションがありました。
関:本番の尺も、かなりキツキツでしたよね。
木内:ですね。水木は長セリフも多かったので「この文章をどう読んだら分かりやすく伝わるのか」と考えながら演じていました。普通の現場ではあまり求められないくらいの速さでしたね。また、オーディションに受かった後、監督から「佐田啓二さん主役の『あなた買います』という白黒映画を参考にしてくれ」と言われたんです。併せて「昭和の戦争が終わってから復興していく社会で、いかに人々が強く生きてきたかということを出したい」という想いも聞いて、力強い水木を作ってくれということだと受け止めました。
 木内秀信
木内秀信
関:僕は小津安二郎さんの作品を参考にしました。作品を見て思ったのは、みんなセリフが淡泊だということ。熱演はあまりなさらず、感情で説明をしないんです。でも、小津さんの時代の映画って、感情を押し付けなくても、さらっとした言葉でドラマを伝えるんですよね。逆に、観ている側に「あんなにさらっとした顔をしているけれど、心の中では色々なことがうごめいているのでは」と想像させるんです。良し悪しはあると思いますが、それが当時の映画の手法だった気がしていて。今回はそういう見せ方なのかなと思いました。
――なるほど。勉強になります。
関:アフレコでは、監督から「実写的に」というディレクションもありました。アニメーションのセリフや感情表現って、2次元を3次元にするために、ある程度のデフォルメや誇張が必要になるルールのようなものがあると思うんです。でも、本作はそういうのを全部取っ払ったほうがいいと思いました。とはいえ、アニメから離れすぎてはいけない。アニメチックなところからちょっと距離を置いて、実写になるべく近づけるというテイストでお芝居をしました。