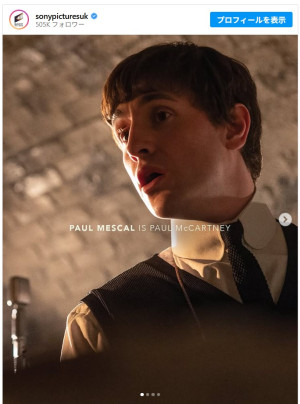「妻夫木さんじゃなかったらできなかった」――妻夫木聡&窪田正孝、沖縄の歴史と魂に向き合う【映画『宝島』インタビュー】

関連 :
戦後、アメリカ統治下の沖縄を舞台に、米軍基地から奪った物資を住民に分け合えることを目的に結成された若者たちの集団“戦果アギヤー”。そのメンバーで、いつか「でっかい戦果」を上げることを夢見るグスク、ヤマコ、レイの幼なじみ3人が、理想と現実に翻弄されながらもがむしゃらに生きていく姿を描いた映画『宝島』。スクリーンに映し出される若者たちの血潮は、観ている者の心にたぎるものを沸き立たせる。そんな魂を込めた映像を作り上げたグスク役の妻夫木聡、レイ役の窪田正孝が、沖縄という土地と歴史への向き合い方、壮絶な撮影の裏側、そして今、この物語を届ける意味や、映画の力について熱い想いを語った。
【写真】妻夫木聡、笑顔がかっこよすぎる! 撮り下ろしソロショット
■沖縄の歴史と魂に、どう向き合ったか
――『宝島』という非常に大きなエネルギーを要する作品への出演を決めた理由、脚本や原作を読んだ際の第一印象からお聞かせください。
妻夫木聡(以下:妻夫木): 役柄よりもまず、原作が持っている圧倒的な熱量をどこまで脚本に落とし込めるか、そもそも映画化できるのかなというのが最初に思ったことです。尺もそうですし、ロケ地として沖縄で撮影ができるのか、基地のことも含めてとにかくお金がかかるだろうなと。役作りというより、そういうことが先に頭に来てしまいました。そこから、改めて沖縄と向き合うというのが自分にとっての一番の課題でした。ただ演じるという次元の話ではなかったので、歴史を学ぶところから始め、当時を生きた方々にもインタビューをさせていただきました。
最終的に僕の核となったのは、親友が導いてくれた佐喜眞美術館で「沖縄戦の図」という絵を見た時です。戦争というものが詰め込まれた絵から、本当に声が入ってきて動けなくなってしまって。絵に「どこかわかった気になっているんじゃないか」と言われた気がしたんです。その時初めて、「感じる」ということを忘れていたんじゃないかと思い至りました。それが、自分にとっての核になりましたね。
 (左から)窪田正孝、妻夫木聡
(左から)窪田正孝、妻夫木聡
窪田正孝(以下:窪田): 僕はまず、キャストとスタッフにすごく惹かれました。妻夫木さんと(『ある男』以来)またご一緒できること、しかも今回はすごく関係性の深い役柄であること、そして大友啓史監督であること。それが一番でした。台本を読ませていただいて、現在の感覚ではどうしても読み込むことができなかった。当時のことをイメージし、携帯もなく、もっとアナログで、隣人とのプライベートもない世界。みんなが家族のような感覚という落とし込み方をしてから読むと、色々なものが紐解けていきました。これは今の時代にこそ描かなければいけない、日本人が向き合わなければいけないテーマなのだと。戦後80年経ちますが、日本はどこまでいっても敗戦国で、その爪痕は沖縄を始め、今の日本中に残っている。エンターテインメントを通して、役者としてこの仕事に携われることはすごく光栄ですし、やる意味をすごく持たせてもらえたのが大きかったです。
■言葉を交わさずとも共鳴した、現場の熱
――オープニングのアクションシーンから凄まじいエネルギーでした。お二人で何か特別な準備や話し合いはされたのでしょうか。
妻夫木: いや、今回本当に、キャスト同士で何か話すってことはなかったよね。
窪田: なかったですね。
妻夫木: もともと窪田くんとは仲は良かったですけど、本格的に芝居をするのは今回が初めてで。お互いを知っているからこそ、話さなくてもいられるというか。窪田くんは彼の中でレイとしての正義に向き合い、僕は僕でグスクとしての正義に向き合って生きていく。そして最終的に基地で感情をぶつけ合うところに向かって、ずっとお互いの人生を生きている感じがあったので、なおさら話さなかった。別に現場で仲が悪かったわけではなく、お互いが匂いで感じ取っていたんだと思います。
 映画『宝島』場面写真(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
映画『宝島』場面写真(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
――大友監督の演出スタイルはいかがでしたか? 細かい指示はあまりされないと伺っています。
妻夫木: 監督から動きの演出はあっても、感情の面で「ああしてくれ、こうしてくれ」というのはほとんどなかったですね。それぞれが思うものを全員がぶつけ合っているような現場でした。
窪田: 監督自身、セリフを求めているわけではなくて、言葉じゃない何かを抉(えぐ)り出そうとしているんですよね。役者というより、一人の人間の中から何が出てくるのかを、ずっとフォーカスしていた。だから、それが出てくるまでOKが出ないんです。沖縄弁が上手く喋れたからとか、そういう表面的なことよりも、その時代に人間が生きていて、食べるものがなかったらどういう行動を起こすのか、どんな顔をするのか。監督の想像を超えていくものを表現していた現場だったと思います。監督の求めるものに行くのではなく、そこにどう映し出すかを試されていた毎日でした。