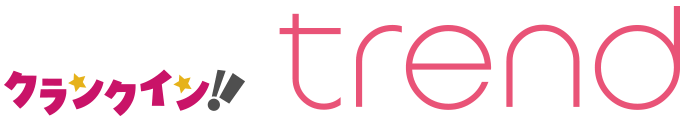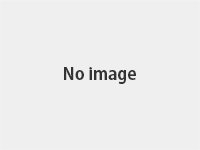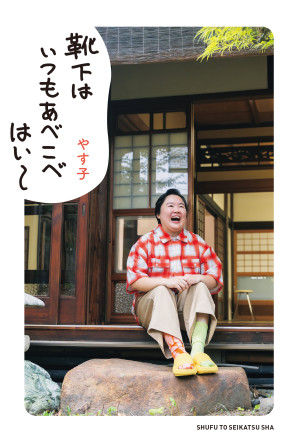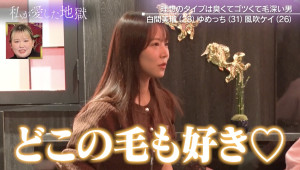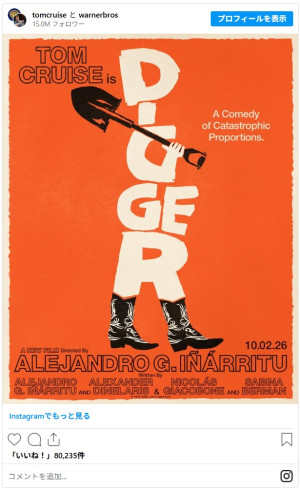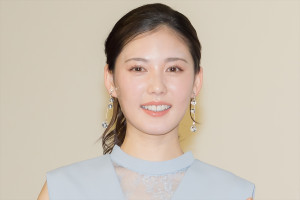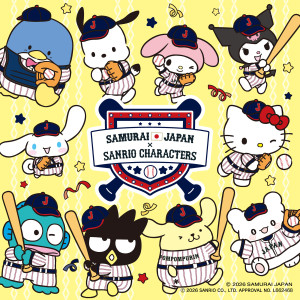溝口健二
溝口健二 出演映画作品
-
祇園の姉妹〈1956年〉
制作年:
溝口健二が戦前に撮り上げた女性ドラマの名作のリメイクは、長回しを多用しないテンポある演出で、より大衆性を増した作品に仕上げられた。人気者の祇園の3芸者は、実の姉妹と姉の娘という組み合わせだ。娘役には中村玉緒が扮し、かわいく健気に演じている。彼女たちの元に、姉と離婚したはずのお坊ちゃん育ちの夫が戻ってきたことから、姉妹の間に亀裂が生じる。
-
紙人形春の囁き
制作年:
1923年に監督デビューした溝口健二が、独自の作風を確立して一躍、注目を集めた記念碑的な無声映画。東京の下町・両国界隈を舞台に、古い商家に育った娘がたどる悲しい運命と一家の末路を流麗な映像のなかに描き出したメロドラマ。柳橋の料亭、浅草仲見世、歳の市などの下町風俗や、大正末期の人情世界を彩り豊かに再現するなど、その後の溝口作品を語るうえで興味深い演出スタイルが散見できる。
-
名刀美女丸
制作年:
戦争も末期にさしかかり、当時の厳しい検閲と自らの作風の間に悩む溝口が発表した芸道もので、溝口らしさが発揮された小品。幕末の世、恩師と仰ぐ小野田小左衛門が暴徒に襲われる。刀師、清音は師の仇を討つため、名刀を作ることに一心不乱となるが、彼には仇討ちは許されない……。
-
藤原義江のふるさと
制作年:
日本初の本格的トーキー「マダムと女房」に先立ち、溝口が手掛けた“ミナトーキー“と呼ばれる部分発声映画。売れない声楽家・義夫とホテルの掃除婦あや子は貧しいながらも幸福な日々を暮らしていたが、あるきっかけで義夫にチャンスが訪れたために二人の仲にヒビが入る……。実際に国際的な声楽家だった藤原義江が主演。
-
虞美人草〈1935年〉
制作年:
夏目漱石の名作を巨匠・溝口健二が映画化。漱石作品が山の手の上流階級の若者を描いた知的で都会的なものであったのに対し、本作品ではそうした人々と並行して描かれる昔気質の庶民の描写に本領が発揮されている。恩師の娘に扮する大倉千代子の演技が絶品。
-
愛怨峡
制作年:
トルストイの『復活』をヒントにした溝口健二得意の女性もので、名作の誉れ高い一作。旅館の一人息子の謙吉と、そこで働く女中おふみは、謙吉の父から結婚の許しをもらえず、東京へ駆け落ちする。だが、東京での貧しい暮らしに耐えきれず、謙吉は実家に戻ってしまう。残されたおふみには謙吉の子が……。
-
ふるさとの歌
制作年:
文部省が懸賞募集した脚本の当選作を日活が委託され製作した教育映画。向学心に燃えながらも、家庭の事情で都会の学校に進学できず村で働いている青年が、休暇で帰省したかつての同級生と再会する。が、その友人はすっかり派手になっており、村にひと騒動が起きる。現存する最も古い溝口健二のサイレンと作品である。
-
歌麿をめぐる五人の女〈1946年〉
制作年:
名作「西鶴一代女」にもつながる江戸風俗を背景として女性を描いた作品。幕府お抱えの絵師と競合して勝ってしまった町衆の画家歌麿を狂言回しとして、水茶屋に勤める気性の激しい娘おきた、美しい御殿女中お蘭などの女たちの生き方を、繊細なタッチで描き出していく佳作。
-
元禄忠臣蔵・後篇
制作年:
前編に続き、本懐を遂げた四十七士の自害までを描く。物語も佳境に入り、ワン・シーン=ワン・ショットを徹底させた溝口演出はさらに重厚さを増す。戦線の拡大で物資が窮乏するなか、厖大な製作費を投入したこの作品は、破格の大作として完成を見た。前編に続き、新藤兼人がセット建築を担当している。
-
元禄忠臣蔵・前篇
制作年:
史実に忠実な真山戯曲の映画化。監督の溝口健二も時代考証には厳格を極め、松の廊下を原寸大で再現したことはあまりにも有名。映画界のスターに加え、舞台で『元禄忠臣蔵』を系統的に上演していた前進座が総出演し、長回しを多用する溝口演出を支えている。セット建築を新藤兼人が担当。
-
武蔵野夫人
制作年:
当時ベストセラーとなった大岡昇平の同名小説の映画化。復員した青年・勉を引き取ることになった宮地家の妻・道子は、やがて勉を一人の男として意識し始める。勉の兄嫁の富子や嫉妬深い道子の夫などが入り乱れて、愛憎の人間模様が展開する……。複雑な心理描写を溝口の独特の演出力で撮り上げた名編。
-
楊貴妃
制作年:
国際映画祭で日本映画が賞を取るようになったこともあり、“これからは合作の時代”と語っていた溝口健二の思いは、この「楊貴妃」での香港との合作によって実現した。玄宗皇帝の妃となった楊貴妃の悲劇的な半生を描くゴージャスなメロドラマ。新しもの好きの溝口の初の総天然色作品。
-
マリヤのお雪
制作年:
原作は川口松太郎となっているが、実はモーパッサンの作品の『脂肪の塊』を翻案したのがこの作品。明治の初め、官軍と西郷軍の戦火が近づいてきたのを知り、町を出た1台の馬車があった。名士たちを乗せたこの馬車には娼婦のお雪たちもいて、軽蔑の視線をうけている。やがて馬車は官軍に捕まり……。
-
宮本武蔵〈1944年〉
制作年:
太平洋戦争のさなかに製作された作品で、内容もともすれば戦意高揚映画に見え、溝口独特のきめの細い演出にも欠ける。当時連載されていた菊池寛の『宮本武蔵』を原作に、一乗寺の決闘から巖流島での佐々木小次郎との一騎討ちまでを描き、武士道と、それに絡む人情を取り上げたあたりは溝口らしい。
-
折鶴お千
制作年:
1929年に「日本橋」1933年に「滝の白糸」と、泉鏡花の原作を見事に映画世界によみがえらせた溝口健二が、三たび泉鏡花をとりあげた名作である。原作の題名は『売色鴨南蛮』。神田明神の境内近くにはいかがわしい商売をして暮らす連中がいた。首領は熊沢といい、若い娘お千も熊沢たちの食い物にされていた。熊沢に養われている少年宗吉は、毎日ただ同然にこきつかわれながらもお千に励まされ生きていた。ある日、あまりの仕打ちに耐えかねた宗吉は、お千とともに熊沢のもとから逃げようと決意するが……。前2作が幻想的なタッチであったのに対し、ここではあくまでもリアリズムに徹して秀逸。
-
女優須磨子の恋
制作年:
夫と離婚して新劇運動に飛び込んだ須磨子は、自由恋愛を説く学者・島村抱月と出会う。新劇界の大スターとなっていく須磨子と新劇運動のリーダーとして活躍する抱月との恋は、やがて悲しい結末を迎えることになるのだった……。溝口=田中の名コンビで描く女性の自立をテーマとした一編。
-
瀧の白糸〈1933年〉
制作年:
水芸人である滝の白糸は、旅興行の先で知り合った苦学生・村越欣弥の、人に媚びないきりりとした性格と将来への夢に惚れこみ、貧乏な村越のために仕送りをして法律を学ばせる。しかし、苦労して借りた金が奪われ、逆上した白糸は高利貸しを刺殺して金を奪い、捕らわれる。彼女を裁くために法廷に立ったのは検事として立派に成長し出世した村越自身だった。昔の恩人を裁くジレンマに苦しむ村越も、ついに法に従い白糸に死刑を宣告する……。名匠・溝口健二が泉鏡花の原作をフラッシュ・バックなどの手法を多用して鮮烈に描いた意欲作。傷んだプリントしか残されていないのが残念。
-
女性の勝利
制作年:
溝口健二の戦後第1作。戦争が終り、政治犯として投獄されていた山岡も釈放される。彼を温かく迎えたのは女性弁護士、細川ひろ子であった。山岡は病院へ運ばれるが、ひろ子は民主化を求める気運のなか、法廷で封建思想の持ち主、河野検事と対決する。女性の自立という問題を強く打ち出した裁判劇。
-
我が恋は燃えぬ
制作年:
明治の自由民権運動の女性闘士で、女性解放運動のさきがけともなった影山英子の『妾の半生涯』をもとにして構成されたメロドラマ。岡山の旧家に育った英子は、恋人の自由党員・早瀬を慕って上京するが、早瀬は実は藩閥政府のスパイだった。傷心の英子は弾圧にもくじけずに闘うが……。
-
赤線地帯
制作年:
国会に売春禁止法案が上程されていた頃、赤線地帯と呼ばれる区域にあった特殊飲食店“夢の里”の主人は、法案が通過すれば売春婦は投獄されると言って女たちを驚かせる。一人息子のために働く女、入獄中の父の保釈金のために働く女、夫が失業しているので通い娼婦をする女、元黒人兵オンリーだった女たち。そんな吹きだまりの“夢の里”にある日、下働きの少女がやってくる。時が経ち法案が4度目の却下となった頃、少女はおそるおそる道往く客に声をかけるのだった。「浪華悲歌」や「祗園の姉妹」を手掛けた溝口健二が得意とする娼婦たちの世界。法案は映画の封切後同年5月に成立。その3ヵ月後の8月24日、溝口は骨髄白血症のため58歳の生涯を閉じた。
-
夜の女たち
制作年:
戦後間もない頃の大阪のパンパン(街娼婦)たちの様々な人生を点描する溝口健二の得意ジャンルの力作。この作品は、溝口が戦中から続いていた低迷状態からようやく抜け出す足がかりとなった。田中絹代が初の汚れ役に挑んでいる。
-
お遊さま
制作年:
谷崎潤一郎の小説『芦川』を巨匠・溝口健二が映画化。美しい未亡人・お遊さまをめぐって展開する妖しく耽美的な世界を溝口の永遠のヒロイン・田中絹代主演で描く。晩年の溝口芸術に大きく貢献した撮影監督・宮川一夫と初めてコンビを組んだ記念碑的作品。
-
西鶴一代女
制作年:
敗戦後低迷を続けていた溝口健二が西鶴の『好色一代女』をもとに、全身全霊を打ち込んで完成させた彼の最高傑作。奈良の荒れ寺へ客にあぶれた街娼たちが集まり、グチを言いあっている。その中に厚化粧でも年は隠せないお春という女がいた。その夜、巡礼帰りの百姓たちの前に引きだされ、“こんな化け猫をおまえたちは買いたいのか”とさらし者になった彼女は、我知らず寺の羅漢堂に入っていく。居並ぶ五百羅漢を眺めやるうちに、羅漢像の一つ一つが過去の男たちに見えてくるのだった。こうして時代は一気にさかのぼり、彼女が御所づとめに出ていた13歳の時からの流転の生涯が綴られていく。様々な男たちと出会い、別れていくたびに不幸になっていくお春を通して、封建制度下に自我を通そうとした女の悲劇を優しく、そして苛烈に描ききっている。溝口一流の長回しが随所で効果を上げており、また巨大なセットの空間の広がりに圧倒される。田中絹代も一世一代といえる名演を見せた。
-
近松物語
制作年:
近松門左衛門原作の『大経師昔暦』を脚色した溝口健二の名作。ふとした偶然で窮地に立たされた男女がやがて真実の愛に目覚め、捕らえられるが嘆くことなく刑場に惹かれていく。いかにも溝口らしい題材を様式的描写の中にパッショネイティブに描ききって、彼の代表作の一つとした。特に家内制手工業を営む経師屋の室内で展開される前半部分は、溝口演出の極致といえる見事なアンサンブル。また、溝口が常に批判してきた長谷川一夫の起用は、かつてない緊張感のもとに最高の演技を引き出すことに成功している。宮中の経巻表装を職とし、傍ら暦の刊行権をも握る“大経師内匠”の手代・茂兵衛は内儀・おさんの兄に銀一貫目を融通したことがばれ、主人の以春に空室に閉じ込められてしまう。おさんは茂兵衛を救うため、かねて夫が言い寄っていた女中のお玉と寝所を取りかえ動かぬ証拠を押さえようとする。ところが深夜忍んできたのはお玉に別れを告げに来た茂兵衛で……。戦前から溝口作品を担当してきた彼の盟友ともいえる水谷浩が美術を担当している。
-
祇園の姉妹〈1936年〉
制作年:
日本を代表する映画作家・溝口健二監督の代表作である。京都の芸者の姉妹を主人公として、人情に厚い姉と打算的で気の強い妹という二人の対照的な生き方を描きながら、どちらも男にもてあそばれてみじめに捨てられていくという女の現実を、きびしい目で捉えた作品。芸者姉妹を演じた梅村蓉子と山田五十鈴も見事にその対照を演じ分け、非情な世界に生きる女性の哀感や怒りを充分に表現しつくした。全体的なテンポは男たちとのやりとりなどユーモラスな面もあり軽い感じも与えるが、克明な京都の風物描写もあいまってずっしりと観ごたえのある一編。依田義賢の脚本も冴え、まさに溝口芸術の一級品である。
-
噂の女
制作年:
溝口健二監督が3度目のヴェネチア映画祭受賞作「山椒太夫」の次に撮った現代ものの小品。京都の色街・島原を舞台に、女手一つで廓を経営する母と、母の商売に疑問を持つ娘との葛藤を描く。監督としての活躍を始めた田中絹代が最後に出演した溝口作品。
-
新・平家物語
制作年:
吉川英治の歴史小説『新・平家物語』を映画化した3部作の第1作。平安末期、次第に力をつけてきた武士階級。若き平清盛はそんな中で権力の野望を胸に、勢力を伸ばしていく。長回しを基調としたカメラワークはフランス・ヌーヴェル・ヴァーグの人々に絶賛された。なんといっても市川雷蔵の若武者ぶりが素晴らしい。
-
雪夫人絵図
制作年:
旧華族の家に生まれた雪が、養子に迎えた夫の暴虐放蕩に身も心も踏みにじられ、ひそかに愛する青年を心に想いながら湖に身を投じて果てる。小原譲治の光と影を抑えた軟調の撮影が艶麗な画面を作る。特に夜の寝室の場面は息をのむ美しさ。
-
残菊物語〈1939年〉
制作年:
歌舞伎界の御曹子・菊之助が、芸の未熟さを子守り女にいさめられ、旅回りの一座で修行を重ねて一人前になるまでを描いた芸道もの。当時、一連の“銭形平次”もので人気絶頂の長谷川一夫が菊之助を演じる。
-
山椒大夫
制作年:
平安時代の末、越後を旅していた母子連れは、人買いにだまされて引き離されてしまう。安寿と厨子王丸の二人の子供は、丹後の大地主・山椒太夫の荘園に奴隷として売られ、毎日苛酷な労働に苦しめられる。山椒太夫のもとで10年間を耐え忍んだ姉弟はある日逃げ出す決心をして荘園を出るが、追っ手が迫り、安寿は弟を救うためにおとりとして池に身を投げる。厨子王丸は逃げ延びて国守となり、母を求めて佐渡に赴く……。森鴎外の小説で有名な話を溝口健二が重厚な演出で描いた秀作。ラストのパン撮影で捉えられた海のシーンは息をのむほど美しく、ジャン・リュック・ゴダールがのちに「気狂いピエロ」のラストで再現した。
-
浪華悲歌
制作年:
溝口健二、戦前の代表的傑作。社会的な弱者である女性の精神の自立を描いて、従来のメロドラマ的女性映画のカラを打ち破った画期的な作品。大阪の薬種問屋に電話交換手として勤めるアヤ子は、会社の金を横領した父親のために、問屋の主人の妾となって借金を肩代りしてもらう。しかし、いつしか主人の妻が知ることになり追い出されてしまった。おまけに兄の学費稼ぎのため、好色な株屋相手につつもたせを仕組むことになる。逮捕され、恋人にも裏切られたアヤ子は家に帰るが、誰も温かく迎えようとしない……。全体に暗いトーンの中でロングショットが多用され、その中に浮かび上がる山田五十鈴の美しい横顔が印象的。
-
浪華悲歌
制作年:
溝口健二、戦前の代表的傑作。社会的な弱者である女性の精神の自立を描いて、従来のメロドラマ的女性映画のカラを打ち破った画期的な作品。大阪の薬種問屋に電話交換手として勤めるアヤ子は、会社の金を横領した父親のために、問屋の主人の妾となって借金を肩代りしてもらう。しかし、いつしか主人の妻が知ることになり追い出されてしまった。おまけに兄の学費稼ぎのため、好色な株屋相手につつもたせを仕組むことになる。逮捕され、恋人にも裏切られたアヤ子は家に帰るが、誰も温かく迎えようとしない……。全体に暗いトーンの中でロングショットが多用され、その中に浮かび上がる山田五十鈴の美しい横顔が印象的。
-
雨月物語
制作年:
上田秋成の『雨月物語』から『朝茅が宿』『蛇性の婬』の2編を取り出して脚色された溝口健二の名作。戦国時代、琵琶湖にほど近い村に住む源十郎は、戦乱に乗じ一獲千金を狙い、自らの焼いた陶器を売ろうとして、侍になることを夢見る義弟の藤兵衛、そして反対するそれぞれの女房を連れて琵琶湖を渡る。その後、離れ離れになった彼らのうち、藤兵衛は大将の拾い首をして出世を果たすが、妻の阿浜は娼婦に堕ちてしまう。一方、妻・宮木が子とともに決死の覚悟で村へ戻ろうとする中、源十郎は死霊に見そめられ悦楽の日々を送っていた……。全編に宮川一夫のカメラが冴えわたり、特に源十郎と死霊・若狭のシークエンスにおいては幽幻妖美の世界がたぐいまれな映像美として結実している。若狭を演じた京マチ子の美しさ、彼女に仕える老女・右近の不気味なシルエットは忘れられない印象を残す。対する宮木役の田中絹代は母性の優しさを感じさせる好演。第14回ヴェネチア映画祭銀獅子賞を受賞した。
-
祇園囃子
制作年:
溝口の得意とする花街を舞台とした作品で、前作「雨月物語」で脚本を担当した川口松太郎が原作を、依田義賢が脚本を担当している。祇園ではちょっと名の知れた勝気な芸者・美代春は、舞妓志願に来た少女・栄子の熱心な頼みに負け舞妓に仕込むことを決心。1年間栄子は芸事に励み、いよいよ舞妓として売り出す日がくる。栄子は現代っ子らしい振舞いが評判となり、楠田という男に目をつけられるが……。溝口に大抜擢された若尾文子、ベテラン・浪花千栄子、進藤英太郎の演技が光る珠玉の作品。とりわけ、祇園になじみの且那・楠田に迫られて、大騒ぎしたあげくに男の唇を噛み切るという大胆な行為に及ぶ、芸妓の卵・若尾文子の奔放ぶりに目を見張らされる。
最新ニュース
-

“令和の峰不二子”阿部なつき26歳、タイトな白ニット姿が「スタイル抜群」「美しすぎる」と絶賛の声
-

石原良純、『ドラえもん』大みそかスペシャルにゲスト出演 のび太たちの前に立ちはだかる悪役を熱演「ドラえもんワールドを垣間見られて光栄!!」
-

やす子、初の書籍『靴下はいつもあべこべはい〜』来年1.30発売決定「どんな気分のときでも読めまーす!」
-

マコーレー・カルキンが判定 『ダイ・ハード』はクリスマス映画なのか? ブルース・ウィリスの答えも
-

舞台『劇場版モノノ怪 前日譚~二首女(ふたくびおんな)~』2026年5月上演決定 「劇場版モノノ怪」シリーズの前日譚を描く完全新作エピソード
-

稲垣吾郎が英国初演から80年愛され続けた舞台に挑む! 『プレゼント・ラフター』公演ビジュアル解禁
-

元NMB48白間美瑠“好きな男性のタイプ”に驚き「どこの毛も好き」「臭ければ臭いほど男らしさを感じる」
-

トム・クルーズ新作は“大惨事コメディ”! アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督とタッグ『DIGGER/ディガ―』2026年公開決定
-

2年片思い中のグラドル美女、“相性”への不安なし「余裕で受け入れられる」
-

北香那、撮影で1日に7杯のラーメンを食べた「ハッピーな気持ちでしかなかったです」
-

相田翔子「我が家の晩御飯」 手作り料理に絶賛の声
-

ナイナイ岡村インスタにとんねるず石橋が登場「元気そうで何よりです」
-

INI・尾崎匠海、國村隼の存在で俳優としても成長「ありがたかった」
-

グラビア話題の43歳・元NHKアナ、タイトなニット姿が「スタイル抜群」と絶賛の声 ミニ丈も履きこなす
クランクイン!トレンド 最新ニュース ›
おすすめチケット
おすすめフォト
おすすめ動画 ›
最新&おすすめ 配信作品 ›
注目の人物 ›
-

X
-

Instagram