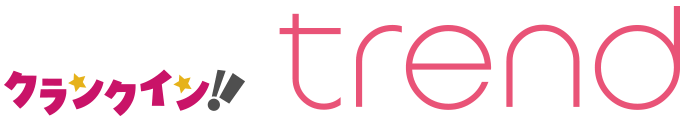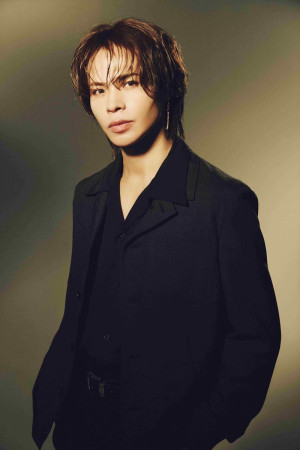『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝』 物語に流れる“少女マンガの血”が意味するもの
■日本の少女マンガが描き続けてきたものとは
「少女マンガの神様」と呼ばれるマンガ家・萩尾望都は、イタリアで少女マンガの歴史について講演した際、手塚治虫の『リボンの騎士』から紹介を始めている。
『リボンの騎士』は、中世ヨーロッパの架空の国を舞台に、女の心と男の心を持って生まれたサファイア姫が、王位継承のために男として育てられるという物語だ。萩尾によれば、このマンガを読んだ当時の女の子たちは、「『もし自分も男の子だったら…』と思いながら、サファイアと一緒に冒険を楽しみました。この『もし男の子だったら』というテーマは、『リボンの騎士』以降、頻繁に日本の少女マンガの中で扱われます」(『私の少女マンガ講義』新潮文庫)と語っている。
講義は『リボンの騎士』にはじまり、『ベルサイユのばら』や『ポーの一族』を通り、『エースをねらえ!』や『キャンディ・キャンディ』、BLジャンルの台頭から『BANANA FISH』や『NANA』などを経由し、最後は、架空の江戸時代を舞台に男女逆転の世界を描いた『大奥』の紹介で終わる。
この講義で萩尾は、なぜ日本の少女マンガが「もし男の子だったら」というテーマを描き続けてきたのかについて明確に解答している。萩尾は、日本の少女マンガは時代ごとに「少女たちが夢見た美しいものや暮らし、生きかた、憧れを描いてきた」(『私の少女マンガ講義』新潮文庫)ものだと語る。少女マンガにおけるジェンダーの逆転や攪乱(かくらん)する物語は、女性ゆえの不自由さから解放されて、自由になりたいという女性たちの夢を反映しているのだ。