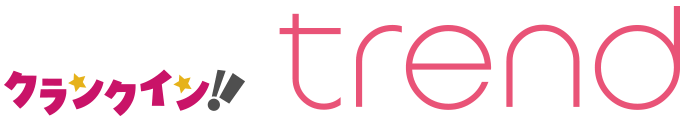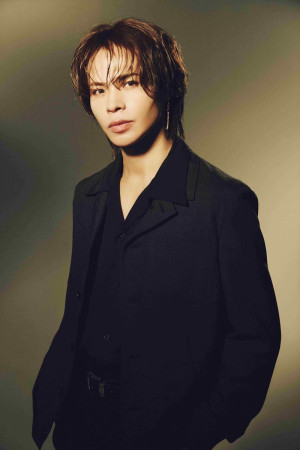『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝』 物語に流れる“少女マンガの血”が意味するもの
■不自由な「牢獄(学校)」で展開される束の間の自由
では、『外伝』はどのような点で少女マンガ的だと言えるだろうか。
本作は2つの物語で構成されている。前半はヴァイオレットとエイミーの物語で、後半はエイミーの妹テイラーがヴァイオレットを訪ねてくることから始まる。とりわけ、少女マンガ的なのは前半だ。
舞台は全寮制の女学校。本作の世界観考証の鈴木貴昭によると、この学校は、アンシェル王国が芸術と文化の最先端の国であることを重要な外交カードにしていたため、貴族女性の教養低下を防ぐ目的で設立されたとある(本作ブルーレイの特典リーフレット参照)。つまり、貴族女性に社交界デビューのための基礎的な教養と振る舞いを身に付けさせる目的で設立され、それが政略結婚などのために必要とされるものだったのだろう。この世界では、女性は政治の道具なのだ。テレビシリーズ第5話では、そんな政略結婚を自分の恋の成就のために、したたかに利用するシャルロッテ姫のエピソードが描かれた。
エイミーも、貴族の振る舞いを身に付けさせ、しかる場所に嫁がせるために不本意に入学させられた。それゆえ、学校は閉じられた牢獄のイメージで描かれる。
全寮制の学校は、少女マンガでは定番の舞台の1つだ。閉じられた箱庭の中で、不自由を強いられながら、友情や恋心が支えになる。少女マンガはそんなドラマを数多く紡ぎあげてきた。
この牢獄の学校において、ヴァイオレットはエイミーに、束の間の夢を見せる存在だ。依頼に応じてどこでも駆けつける自動手記人形であるヴァイオレットは様々な場所を移動できる。その自由がエイミーにはない。エイミーが天井を見上げると、そこには空と鳥の絵が描かれている。鳥のように自由になりたいが、絵の鳥はどこにも行けない。牢獄に囚われたエイミーの気持ちを代弁しているかのように。
エイミーの一人称が「僕」であるのも印象的だ。これは男のように自由に生きたいという少女マンガ的な願いにも通じるが、本作ではそれを逆手にとって、複雑な環境に囚われたエイミーの描写に利用する。
原作小説では、エイミーの出身地は貧しい娼婦街となっている。エイミーは、髪も短く少年のように振る舞っていたが、原作者の暁佳奈はその理由を「女が趣味でもなく男装をしているのならば理由はほぼ貞操を守るために限られるだろう」と書いている(KAエスマ文庫『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝』P93)。
彼女の一人称が「僕」なのも、おそらくその出自が関係しているのだろう。男の方が自由だからというより、女ではまともに生きられない環境だったから男装をしていたのだ。
そんなエイミーは、女学校で淑女の教育を受ける中で、「僕」ではなく「わたくし」という一人称を使わねばならなくなる。女として生きるのが困難な環境を生き抜くために身に付けた「僕」の一人称を、今度は女性の役割を押し付けられた挙句、捨てねばならない。
エイミーはある日突然、父と名乗る貴族に引き取られ、ほとんど選択の余地なく貴族の娘となることを強いられた。そのような家父長制の横暴に翻弄されたエイミーにとって、異性は不自由を強いる存在にすぎない。
だから、彼女に自由を見せられるのは異性ではなく、同性のヴァイオレットなのだ。「騎士姫」と呼ばれるヴァイオレットこそがエイミーに自由を見せる「王子様」として振る舞える。
デビュタントでヴァイオレットが着る衣装はそのことを強調する。パンツルックの男性用タキシードのような意匠が混じった服を身にまとい、エイミーをやさしくリードして華麗なワルツを踊るヴァイオレットは、『ベルサイユのばら』のオスカルを想起させる。
デビュタントが終わればヴァイオレットは学校を去り、束の間の夢として、前半の物語は幕を閉じる。学校の外門が、まるで牢屋の鉄格子のようにエイミーとヴァイオレットを分断している。だが、彼女がヴァイオレットに託した手紙だけは、その牢獄の外に出て、最愛の妹に届くのだ。