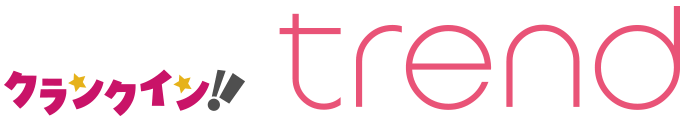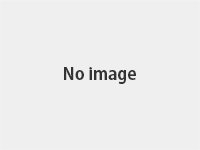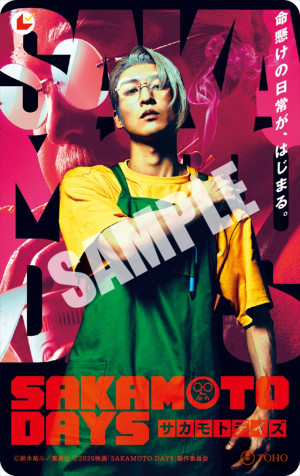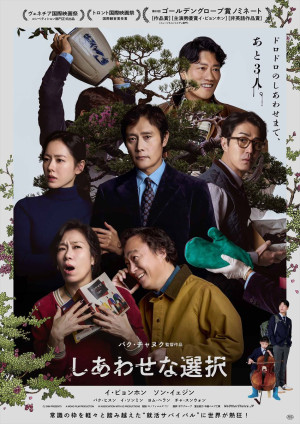斎藤一郎
斎藤一郎 出演映画作品
-
日本侠客伝 白刃の盃
制作年:
銚子の博徒・外川一家は堅気の運送業を始め、順調に繁盛していた。一方、元幹部の根占は外川運送の乗っ取りを企らんでいた。東京から流れてきた風来坊の大喜多俊二は、一家の温かい人情にふれる。根占のあまりの無法ぶりに、俊二は死を覚悟で殴り込んだ。
-
眠狂四郎無頼控 魔剣地獄
制作年:
1956~58年に東宝で鶴田浩二の眠狂四郎シリーズが3本作られたが、これはその3作目。将軍の娘・高姫を操る薬種問屋“相模屋“は、老中が隠匿した五万両を狙うとともに、ニセ狂四郎に辻斬りをさせ江戸を恐怖に陥れていた。短命に終わったシリーズだが配役は豪華である。
-
悪名波止場
制作年:
朝吉と清次は四国からの帰りの船中、だまされて鬼瓦のところで働く羽目になる。そこで、鬼瓦一味が麻薬の密売で悪どくもうけていることを知り、怒った二人は鬼瓦一味を叩きのめすのだが……。水原弘がヒモ役をニヒルに演じる。
-
月姫系図
制作年:
武田勝頼の遺宝ををめぐる浪人と旗本娘の活躍を描いた伝奇娯楽アドベンチャー。遺宝の秘密は“風林火山“を象る4枚の枝折に託され旗本娘の雪絵が“風“を浪人の進太郎が“山“を持っていた。だが“林“の枝折を持つ奉行が忍者を使ってすべての枝折を集めようとする。謎は能面をつけた女“月姫“のみが知っているのだが……。
-
修羅桜
制作年:
松竹映画3000本記念作品。将軍家斉の治世。老中・大野備前守は、幕府転覆を企て、その資金として、大阪城に隠してある黄金300貫を江戸まで、岩波半兵衛に運ばせようとする。半兵衛は道中で黄金の使い道を不審に思い、どこかへ隠した。半兵衛は幽閉され、その息子・又四郎は、消えた父と黄金を探すが……。次々に登場するスターの顔ぶれも楽しい。
-
流れる星は生きている
制作年:
戦争が終わり、夫とはぐれた妻のけい子は3人の子供を連れて日本へ帰って来た。引き揚げ寮に住みながら夫の帰りを待つけい子。彼女の働き先の製本所主人は、次男を引き取りたいと申し出る。しかし、それを知った子供たちは家出をしてしまう……。藤原ていの記録文学を映画化した、三益愛子主演の“母もの“人情映画。
-
陸軍中野学校 密命
制作年:
イギリス諜報機関極東キャップ“キャッツ・アイ“の正体を暴くために中野学校より密命が下る。それを受けた椎名次郎が発見した意外な人物とは……。サスペンス・タッチで描かれた本作は、犯人探しの面白さが加味され、良質のミステリーとなっている。
-
月の出の決闘〈1960年〉
制作年:
原作は川口松太郎の『利根川鴉』。片腕のない旅鴉・枡形の朝吉は、ある湯治場で死んだ女房そっくりの声を持つ、お安と出会う。お安は宮大工・徳次郎の妻だったが、今の徳次郎は右腕が利かず、しかもバクチ狂。その徳次郎が、事件で死んだお安を、朝吉が殺したと勘違いして……。役者として転期を迎えた、「不知火検校」直後の勝新太郎が、片腕の渡世人、朝吉を好演。
-
母に捧ぐる歌
制作年:
夫を病で亡くした女給上がりの紀子は、昔気質の姑に娘を奪われ、亡夫の薬代の返済のため、上海に流れていく。母を慕う娘は、生前、父がコンクールに応募して入賞した曲「母に捧ぐる歌」を発表会の舞台で歌い上げる……。母子の愛を描いた少女哀話。主題歌の吹き替えは、歌上艶子と中村淑子が担当。
-
処女宝
制作年:
前年「銀座カンカン娘」をヒットさせた島監督が作ったメロドラマ。真弓は劇作家の船田と愛し合っていたが、豪華な生活に惹かれて金持ちの義太郎と結婚する。傷ついた船田を勇気づけたのは真弓の妹・真金であった。船田は真金に励まされ、次々と作品を書くようになり、名声を得る。高杉と高峰が性格の違う姉妹を好演。のちのTV放映時には「競う美女姉妹」と改題された。
-
幡随院と白柄組 男の対決
制作年:
おなじみ幡随院長兵衛と水野十郎左衛門の葛藤を描いた娯楽時代劇。家光治世下、ことごとく対立する幡随院と白柄組。そんな中幡随院一家にシンパの塩問屋阿波屋をはじめ、ほとんどの江戸の塩問屋が、勘定奉行松坂、老中戸田と組む相模屋によって暖簾をおろす寸前に追い込まれる。
-
放浪記〈1954年〉
制作年:
ベストセラーとなった林芙美子の自伝的小説を、久松静児が映画化。同作品は1935年に木村荘十二監督で、1962年に成瀬巳喜男監督で映画化されている。行商人の子として各地を歩き、カフェの女給をしながら詩作をするヒロインを角梨枝子が好演するが、夏川静枝主演の木村作品、高峰秀子主演の成瀬作品の味わいには及ばない。
-
泥にまみれて
制作年:
志乃は学生時代、鶴岡知而と知り合い結婚した。やがて長女が生まれ、知而は劇作家として成功するが、当局の弾圧で公演は中止、劇団員は留置される。嫁いだばかりで夫の浮気から実家へ帰ってきた長女に、志乃が自分たちの夫婦の足跡を語って聞かせる形で、ストーリーが進行。苦労ばかりで泥にまみれた20年の女の人生模様をじっくりと描き抜いた女性映画。
-
てんやわんや次郎長道中
制作年:
黄金騒ぎに沸く宿場町にひょっこりと現れた若き旅鴉は、やがて町のゴタゴタに巻き込まれていく。果して、この二枚目旅鴉の正体は? 市川雷蔵のほかは関西喜劇陣がズラリ勢ぞろいの時代劇コメディ。森一生監督によるひょうひょうとした演出と、雷蔵のおとぼけ演技も見ものの一つだ。
-
面影三四郎
制作年:
姿三四郎の得意技“山嵐“を受け継ぎ、面影三四郎と呼ばれる宇津木。戦後、一時彼はヤクザのボスの手先となるが、柔道は暴力ではないと悟り、更生。最後は、横暴なヤクザに対し、正義の山嵐をふるう。「姿三四郎」の原作者・富田常雄の原案。かつて姿三四郎に扮した藤田進主演と、すべて姿三四郎の現代版。藤田の職業が車引きならぬ、タクシー運転手というのが面白い。
-
曉の門出
制作年:
戦場より帰還した傷病兵・川村新太郎は、意中の恋人が親友の妻になっていることを知り、故郷を捨てて東京に出る。彼はそこで失明した上官や戦争未亡人が強く生きていく姿に接し、再び故郷の農村に戻って親友と和解する。軍事保護院後援の時局映画。田を守る農民の姿に戦場を重ね、国民精神を鼓舞しようと計った。
-
お富と切られ与三郎
制作年:
以前は深川で芸者をやり、今は土地の親分の妾にされている女・お富と、彼女を見染めたため親分にメッタ斬りにされ、海へ投げ込まれた男・与三郎の悲恋を描いた時代劇。復讐劇も加えて壮絶な仕上がりに。全身に無数の傷を負いながらも与三郎は生きのび“切られ与三郎“として江戸に現れるが……。
-
花の幡随院
制作年:
ことごとく対立する旗本無頼・水野十郎左衛門を頭目とする白柄組と、町奴・幡随院長兵衛の一家。長兵衛一家の食客となった白井権八は、子分・極楽十三とともに吉原に遊びに行った折、白柄組と出会い乱闘になる。その時、十三は誤って水野の仲間・惣平を斬ってしまい50日の牢入りとなった。その頃、権八を仇と狙う別の兄弟がいて……。多彩に展開する任侠時代劇の佳品。
-
若妻
制作年:
日活大将軍時代、脚本家・如月敏とのコンビで新婚もののブームを作り、そのモダンな感覚が高く評価された伊奈精一監督のメロドラマ。夫の理由なき嫉妬によって、愛する一人娘とはなればなれになった若妻の苦しみと母子愛を、確かな演出で描く。松島詩子と岡晴夫が主題歌を歌っている。
-
剣に賭ける
制作年:
剣豪・千葉周作の若き日の姿を市川雷蔵が熱演する時代劇。剣の修練のみを考える周作は、江戸の剣聖・浅利又七郎道場に入門するが、門下生の高柳又四郎の“音無しの構え“に打ちのめされて以降、すさまじい執念で剣の腕を上げていく。しかし、彼にはかつて赤子を斬った罪の意識が深く心に残っていた。
-
忍びの者 新・霧隠才蔵
制作年:
大阪夏の陣で豊臣家が滅亡したあと、駿府に潜み、家康暗殺を狙う霧隠才蔵率いる伊賀忍者たちの活躍を描く。徳川方は風魔一族を警護にあて伊賀ものを次々と殺していく。才蔵は駿府城潜入に成功するが……。ラストの風魔大十郎と才蔵の一騎打ちが迫力十分。
-
眠狂四郎 円月斬り
制作年:
家斉の隠し子が将軍の世継ぎを狙って暗躍する。マザコンで刀剣マニアである彼は、狂四郎の“無想正宗“に魅了され、我がものにせんとたくらむ。狂四郎は刀のためし斬りにされた男の遺児とともに彼らの陰謀を断つ。脇役、特に女優に魅力が乏しく、話もご都合主義が目立つ。
-
座頭市鉄火旅
制作年:
例によって座頭市が、悪徳親分をこらしめるというストーリーだが、クライマックスの大殺陣で樽の中に入れられグルグル回された市が“盲にゃまわる眼がねェ!“と啖呵をきって、樽の中から樽ごと敵を斬り捨てるという趣向は面白い。
-
日本侠客伝 昇り龍
制作年:
前作に続き、若松が舞台。小頭組合の結成を呼びかけた玉井金五郎は、共同組の友田に狙われる。傷ついた玉井を救ったのはお京だった。お京は畢生の昇り龍を玉井の背中に彫り込む。傷が癒えたのもつかの間、玉井と友田の争いは新たな局面を迎える。
-
女囚と共に
制作年:
他の娘と結婚した無情な男の新居に放火した女、前科11犯の窃盗犯、年若い夫を殺して乳幼児を抱えた女など、女子刑務所囚人たちの様々な生態を描き、その矯正補導を主題とした異色の社会派ドラマ。木暮・久我・岡田・香川らが女囚人を好演。
-
弥太郎笠
制作年:
子母沢寛の原作を、大映時代劇の名匠・森一生が監督した股旅任侠映画。旗本直参の家柄に生まれながら、武士を嫌ってヤクザになった、りゃんこの弥太郎の旅と恋心を描く。かつて親分だった虎太郎の娘を慕う弥太郎は、虎太郎を暗殺して悪徳をつくす大八一家に挑戦し、娘を守りぬいていく。
-
悪名太鼓
制作年:
清次は狼王会の菊沢にだまされて、朝吉の大事にしていた太鼓の胴に5億円の密輸品をつめて関西ルートに流す手伝いをするハメに。しかし真相を知った二人の活躍で、悪党一味は残らず逮捕される。
-
銭形平次捕物控 人肌蜘蛛
制作年:
3年前、材木買い占めの罪を上総屋と尾張藩にきせられた新吉が流刑地から脱走した。一方、新吉の弟・新次郎が兄を捜しに江戸へ出てきたが、彼は上総屋の娘と恋に落ちる。その時から謎の連続殺人事件が始まったのだが……。
-
桃太郎侍
制作年:
1952年に長谷川一夫主演で映画化された山手樹一郎の同名小説の再映画化。双子を忌む武家の風習から里子に出され、成人して無類の剣の使い手となった桃太郎。そのころ生家の若木家では次席家老の陰謀により、若殿新之助が危機にさらされていた。桃太郎は身代わりとなって敵に立ち向かうことを決意する。
-
若き日の信長
制作年:
時は、戦国。若き信長は、尾張八ヵ郷を治め、清州城で駿遠三ヵ国の領主・今川義元と対していた。歴代織田家に仕えていた山口左馬之助は、今川方の優勢に屈し、今川のスパイとなったが、遠謀深慮の武将・信長はすべてを見抜いていた……。大佛次郎の歌舞伎劇を、多作・絶頂期の森一生監督が折り目正しく映画化している。
-
かげろう絵図
制作年:
松本清張の同名小説を、名匠・衣笠貞之助が映画化。徳川十二代将軍・家慶の頃、隠居した前将軍の権勢が今だ幅を利かせているなかで、世継ぎ問題をめぐり、腐敗堕落した大奥と幕府内部が繰り広げる派閥抗争を描く。大道具や小道具にこだわる衣笠の注文を受け、美術担当の西岡善信が、江戸城内や市街をぜいたくなセットで再現している。
-
眠狂四郎 魔性剣
制作年:
狂四郎がふとした因縁で知り合った大工の孫・鶴松は実は岩代藩主の妾腹であった。世継ぎのできぬ岩代藩は一度は殺そうとした鶴松を誘拐するが……。他に第2作で死んだむささびの伴蔵の妹が登場、狂四郎の行手をさえぎる。
-
日本侠客伝 浪花篇
制作年:
横浜日東組の代貸・藤川宗次は、作業中に死んだ弟の骨を引き取りに大阪の浪花運送に現れた。浪花運送は半田組の仕事を奪おうといやがらせを繰り返している。宗次は半田組に味方し、その窮地を救う。が、沖仲仕・寅松を殺され、宗次の怒りは爆発する。
-
江戸へ百七十里
制作年:
津山十万石藩主小森家の落としダネである長谷部兵庫は、お家との絶縁条件として大金を手に入れ、フラリと旅に出る。その道中、松平福姫と知り会った兵庫は、彼女が翌日兵庫そっくりの小森家嫡男とお見合いさせられることを知るが……。市川雷蔵が一人二役で剣の冴えをみせる明朗時代劇。
-
日本侠客伝 斬り込み
制作年:
新宿では、露天商の自由組織・街商同盟と、縄張りの拡張をもくろむ相州一家が対峙していた。子連れの渡世人・中村真三は、中村一家の名乗りをあげ街商同盟を守る。仲裁に入った若松一家の親分が倒され、中村一家の面々は、相州を叩き潰さんと立ち上がった。
-
十代の性典
制作年:
思春期映画のはしりとなったシリーズの第1作。17歳の高校生房江、同級生の英子、上級生のかおるらを中心に彼女のボーイフレンドたちと織り成す、愛と性を描く。他愛ない内容ではあるが、当時にしてはショッキングで、学生に見ることを禁ずる学校もでたほどだ。不幸な結末を迎える女学生たちの姿が悲しい。
-
美貌の都
制作年:
大阪の町工場で働く千佳子は、同じ工場で働く恋人、耕一がいながら、貧しい生活から脱して陽の当たる場所にいきたいと願っていた。そんな彼女の前に現れた青年副社長、一彦。千佳子は彼の住む夢のような世界の虜となり、耕一を冷たくあしらい、工場を辞めてしまうのだが……。
-
眠狂四郎 女妖剣
制作年:
エロチシズムを前面に出し、抜群の面白さを誇る第4作。淫欲とアヘンに溺れる将軍の娘・菊姫、隠れキリシタンの情報と引き換えにアヘン密輸を黙認されている備前屋、狂四郎と血のつながりを持つという聖女のぴるぜん志摩、この3者に狂四郎が絡み、浜松で意外な結末を迎える。狂四郎に志摩の情報をもたらした隠れキリシタン島蔵と妹・小鈴の処刑場に狂四郎が斬り込むシーンのロングと横移動のあざやかなカメラワーク、大小二刀による狂四郎の見事な居合い。そして第1作以来の宿敵・陳孫との闘いなどアクション・シーンが最高。己れの前に肉体をさらす聖女を一刀のもとに斬り捨てるラストの切れ味も抜群だ。
-
次郎長富士
制作年:
長谷川一夫以下大映オールスター・キャストによる“次郎長富士”ものの一編。秋葉の火祭りで売り出した次郎長一家が、富士川川原で黒駒一家と大喧嘩するまでを講談調で描いた一大娯楽作品。勝新太郎の森の石松がはまり役。
-
愛妻記
制作年:
新進作家の多木太一は妻とも別れ、のんきに一人暮らし。学生である後輩が妻と営む麻雀クラブの手伝いなどをしていた。その店には彼女の友人、芳江が働いている。太一は明るい彼女にひかれていき、ついには結婚をするのだった。貧しいながらも幸福に生きる夫婦を温かいタッチで綴る。
-
座頭市千両首
制作年:
代官の陰謀で千両箱強奪事件の犯人という汚名を着せられた座頭市は、真相を解明し代官一味と用心棒の十四郎を斬る。城健三朗扮する用心棒が馬に乗り鞭を振り回して市と対決する、西部劇タッチのアクションは迫力十分。
-
大いなる旅路
制作年:
大正末期から満洲事変、日支事変、そして大東亜戦争へと移る激動の時代。ある事故を機に、列車の安全に生涯をかけようと誓った一人の国鉄機関士・岩見と、その家族の波乱に満ちた半生を30年にわたって描き出した人間ドラマ。新藤兼人のオリジナル・シナリオを、社会派・関川秀雄がヒューマン・タッチで映像化した。
-
日本侠客伝 血斗神田祭り
制作年:
老舗を誇った神田の呉服問屋“澤せい”も、このところ商売が思わしくなく、借金がかさむ一方だった。澤せいの土地家屋を狙う大貫一家は、若旦那の伸夫から権利書を取り上げ、伸夫もろとも澤せいを焼き払った。纒持ちの新三をはじめ、神田“よ組”の連中は澤せいの再建に力を貸す。大貫は訴訟を妨害するため、伸夫の女房・花恵を連れ去る。新三は花恵を救うため大貫一家に乗り込んだ。
-
千姫御殿
制作年:
豊臣家が滅亡した大阪城落城の折、助け出された家康の孫・千姫の後半生を描く悲恋物語。本多家へ再嫁した千姫は吉田御殿にこもり遊興にふけっていたが、招き入れられた男は翌日死体となって池に浮かぶのだった。
-
青葉城の鬼
制作年:
山本周五郎の小説『樅の木は残った』の映画化。主人公、原田甲斐は、実説では伊達六十二万石の存続を危うくした、お家騒動の黒幕的存在。これを、実はこの騒動が、老中・酒井雅楽頭の外様大名取り潰しの策謀であるとし、伊達家存続に尽力しながら、一人で罪を背負って死んだ男として、原田甲斐を解釈している。長谷川一夫が、善悪の境界線上で苦悩する甲斐を熱演。
-
続・座頭市物語
制作年:
市がまだ盲目になる前に、一人の女をめぐって争った実兄・与四郎が、凶状持ちの浪人となって市の前に現れる……。市の実兄の浪人を勝新太郎の実兄である城健三朗(のちの若山富三郎)が好演。
-
新選組始末記
制作年:
子母沢寛の原作を三隅研次監督、市川雷蔵主演のコンビで映画化した幕末もの。浪人・山崎蒸は恋人・志満の反対にもかかわらず、当時京都で活動し始めていた壬生の新選組に入るが、内部には策謀が渦巻いていた。近藤勇に扮する城健三朗(=若山富三郎)が好演。
-
川のある下町の話
制作年:
下町のS大附属病院のインターン・義三は川に落ちた少年を救ったのが縁で、その姉のふさ子と知り合う。両親を亡くした彼女は、パチンコ屋で働く貧しい娘だったが、いつしか義三との間に愛が芽ばえていく……。『婦人画報』に連載されて人気を博した川端康成の原作の恋愛もの。
-
日本侠客伝 関東篇
制作年:
築地・魚河岸の老舗問屋“江戸一”は父の亡きあと、男勝りの娘・栄が切り回していた。風来坊の船乗り・緒方勇は、ふとしたことから江戸一で働くことになる。ところが、協同組合の理事長が魚市場を牛耳っていたため、江戸一の商売は思わしくなかった。江戸一が引き受けた外国との取引も、郷田の横槍で失敗に終わった。度重なる郷田の妨害に、勇らの怒りはつのり、河岸を舞台に大乱闘が繰り広げられる。
-
男ありて
制作年:
家族のことをいっさい顧みず、仕事一筋に生きるプロ野球監督・島村。家族に相談もなしにルーキー選手を家に同居させるほどの彼が、ある日1ヵ月の出場停止を命じられ……。ホーム・ドラマには定評のあった丸山誠治が、新たに仕事と家庭というテーマに踏み込んだ作品。撮影は、成瀬巳喜男とのコンビで知られる玉井正夫。志村喬がお好み焼きを焼くシーンと、ラストの妻の墓に語りかけるシーンは、秀逸。
-
夏目漱石の三四郎
制作年:
異才・中川信夫監督が1941年の「虞美人草」に続き再び夏目漱石の名作に挑んだ作品。三四郎に山田真二、美彌子に八千草薫が扮し、大正時代の若者のひそやかな愛と、その挫折を描く。名手・玉井正夫による撮影が素晴らしく、夏目文学の風趣を香り豊かに再現している。
-
三代の盃
制作年:
江戸築地伊三郎一家の三下、政吉は一日も早く親分の盃をもらう日を夢見ている。そんな折、銀座の新興勢力、仁右衛門一家が、築地一帯に異人相手の歓楽街を作り、伊三郎一家を追い出すことを計画。殴り込みに行ったが子供扱いで追い返された政吉は旅に出、3年後、いっぱしの姿になり築地に戻って来た。勝新が暴れる任侠アクションの隠れた名作。
-
かあちゃんと11人の子ども
制作年:
西伊豆に住む農家の主婦が書いた体験談が原作。11人の子供を産み、夫とともに仕事に励んだ母親の子育てと労働の半生を明るくほのぼのと描く、文字どおりの大型ホームドラマ。昭和の時代をたくましく生き抜いた母親を、左幸子が好演。
-
女と味噌汁
制作年:
同じ池内淳子の主演で『東芝日曜劇場』の人気シリーズとなったTVドラマの映画化。美人でしっかり者の芸者・千佳子は、貯金をはたいて買ったライトバンで移動味噌汁屋を始める。庶民性と色気を兼ね備えた池内淳子のはまり役。五所平之助の最後の劇映画。
-
乳母車
制作年:
石坂洋次郎の原作を田坂具隆監督、石原裕次郎主演で映画化した青春映画の佳編。利発な娘・ゆみ子は父が囲っている愛人を訪ねるが、突然の来訪にもかかわらず彼女は明るく娘を迎え入れる。娘は父と愛人の間に赤ん坊が生まれているのに驚いたものの、愛人の弟の屈託ない言動に次第に心がなごんでいく。石坂洋次郎の一種のユートピア的な人間関係を田坂具隆監督は決して力むことなく淡々とした演出で描き、作品に不思議なリアリティーを持たせることに成功した。愛人の弟という複雑な役どころを与えられた石原裕次郎が、“太陽族”映画とはまた違った素直な演技を披露し、好感が持てる。
-
千姫と秀頼
制作年:
徳川家康を祖父に、豊臣秀頼を夫に持つ不遇の姫君・千姫。徳川家の政略の犠牲となった彼女の数奇な生き様をロマン豊かに描き上げた時代劇。千姫役の美空ひばりを、秀頼役の萬屋錦之介、時代劇初出演の高倉健らが盛り立てている。
-
雪割草
制作年:
田坂具隆の戦後第2作として撮られたホーム・ドラマ。郊外の住宅地に暮らす平凡な夫婦の前に突如、夫と別の女との間にできた隠し子が現れる。夫婦の間には微妙な波風が立ち始めるが……。撮影は、田坂作品初期以来コンビを続ける伊佐山三郎。妻役の三條美紀は、大映の元経理課員。
-
どぶろくの辰〈1949年〉
制作年:
第二次大戦末期、広島で被爆した田坂具隆監督の、戦後再帰第1作。監督助手がついているのも彼の健康回復が思わしくなかったためと言われている。道路工事現場で働くどぶろくの辰の女性関係を描いた作品で、原作は新宿ムーラン・ルージュ出身の劇作家・中江良夫による同名戯曲。
-
宗方姉妹
制作年:
『朝日新聞』に連載された長編小説を、松竹の名匠・小津が新東宝の資本で撮り上げた文芸作品。小津が得意とする平坦な日常感覚のリズムを刻む物語とは幾分趣を異にし、原作ものらしいドラマティックな展開が特徴。日本の古い習慣に準じて生きる姉と、束縛されず自由に生きる妹を対照的に描きながら、日本の社会を浮き彫りにしている。夫・亮助が失業し、やむなくバー勤めをする妻・節子。亮助は自信をなくし、暗く心を閉ざしている。夫のある身でありながら、姉がひそかに神戸の家具屋・田代に想いを寄せているのを知る妹・満里子は気が気でない。亮助、田代、そして姉に、満里子は正直な気持ちをぶつけていく。
-
西鶴一代女
制作年:
敗戦後低迷を続けていた溝口健二が西鶴の『好色一代女』をもとに、全身全霊を打ち込んで完成させた彼の最高傑作。奈良の荒れ寺へ客にあぶれた街娼たちが集まり、グチを言いあっている。その中に厚化粧でも年は隠せないお春という女がいた。その夜、巡礼帰りの百姓たちの前に引きだされ、“こんな化け猫をおまえたちは買いたいのか”とさらし者になった彼女は、我知らず寺の羅漢堂に入っていく。居並ぶ五百羅漢を眺めやるうちに、羅漢像の一つ一つが過去の男たちに見えてくるのだった。こうして時代は一気にさかのぼり、彼女が御所づとめに出ていた13歳の時からの流転の生涯が綴られていく。様々な男たちと出会い、別れていくたびに不幸になっていくお春を通して、封建制度下に自我を通そうとした女の悲劇を優しく、そして苛烈に描ききっている。溝口一流の長回しが随所で効果を上げており、また巨大なセットの空間の広がりに圧倒される。田中絹代も一世一代といえる名演を見せた。
-
博徒対テキ屋
制作年:
昭和4年の浅草を舞台に、デパート進出を図る資本家と伝統的テキ屋との対立、さらにはテキ屋同士の内紛に巻き込まれる博徒の姿を描く。菊家一家の息子・竜太郎は、自分が母親の密通からできた不義の子であることを知り、実の父親を殺して一家を飛びだしたものの、浅草のために我が身を投げうっていく。
-
骨までしゃぶる
制作年:
遊廓に閉じこめられ、骨までしゃぶりつくされる運命の遊女が、自由を求めて脱出を図る。加藤泰が撮った初めての“チャンバラのない映画”。彼の映画には欠かすことのできないヒロイン・桜町弘子が、気丈な遊女を体当たりで演じた。
-
稲妻〈1952年〉
制作年:
林芙美子の同名小説を、田中澄江が脚色した成瀬巳喜男=高峰秀子コンビの名作。4人の子供の父親がみな違うという複雑な母子家庭で、母と異父兄姉たちの醜さに愛想をつかした末娘が、家を出て自立する過程を物語の骨子としている。作者はすべての登場人物を肯定も否定もせずありのままに描いており、俳優たちの好演も相まって、類型に属さない生身の人間の存在感が鮮烈に迫ってくる。バスガイドとして働くヒロインを映した冒頭シーンでの車窓からのぞく風景をはじめ、東京という都市の息づかいを捉えている点でも出色で、娘の実家のある下町と新居の世田谷とは見事に描き分けられている。
-
あにいもうと〈1953年〉
制作年:
東京近郊、多摩川べりの田舎町。荒っぽい性格だが妹への愛は人一倍の兄と、いったん東京に出たものの年下の学生の子をはらんで再び兄のもとへ帰ってきた妹の、深い兄弟愛の世界を描いた作品。1936年、江口又吉脚本、木村荘十二監督のコンビで映画化された、室生犀星の同名小説の2度目の映画化。今回の脚本は成瀬とのコンビは定評のある水木洋子。成瀬の全盛期に撮られた傑作で、彼にとっては最後の大映映画でもある。登場人物の小さなしぐさや軽い目配せを緻密に組み立てて、ドラマの情緒をつかんでいく演出はまさに名人芸の域。成瀬の1953年作品に見られる、「夫婦」「妻」そして「あにいもうと」といったタイトルは、彼の作品世界のよって立つ場所を、これ以上ないほど明確に教えてくれる。
-
夫婦〈1953年〉
制作年:
ある地方都市から東京へ転勤してきた安サラリーマン・中原伊作とその妻・菊子。彼らは、妻を失い独り身の武村という男の家に同居させてもらうことになるのだが……。すでにハネムーン気分も遠い昔のこととなった結婚6年目の夫婦が、一人の独身男と生活をともにするなかで、曲折の果てに夫婦の深い愛情を確認し合うに至るまでを描いた、成瀬お得意の小市民ホームドラマ。成瀬が最も充実した作品群を連作した1950年代前半の作品で、水木洋子、中井朝一といったベスト・スタッフが脇を固めている。必要最小限の登場人物で人生のすべてを描ききってしまうシナリオと演出の素晴らしさは驚異的。
-
お茶漬の味
制作年:
戦時中に検閲当局から却下された脚本を戦後になってから映画化。地方出身の商社マンが社長の親友の娘と結婚し、その夫婦が中年にさしかかった時の物語。妻は、旅行に野球観戦にと遊びまわり、夫のヤボったさや田舎者丸出しの習慣を嫌っていた。が、夫の海外出張をきっかけに、彼の頼もしさを見直す。夜中に二人でお茶漬けを食べながら、夫婦は人生はお茶漬けのようなものだと実感する。この作品では、飾らない生活がいちばんだと言う夫の考えを支える、庶民的な生活のディテールが、娯楽(パチンコ、競輪)、食べ物(トンカツ、ラーメン、漬物)、嗜好品(煙草の“朝日”)といったかたちでとり入れられている。若き日の川又昴が撮影助手を担当。
-
山の音
制作年:
原作は川端康成が戦後最初に発表した同名小説。とある中流家庭を舞台に、老境に入った男が、同居する若く美しい息子の嫁に抱く複雑な感情を綴っている。下町を愛し、市井に暮らす人々の日常を描いてきた成瀬の作品歴においては異色の題材。だが、日本的なものをめぐる川端独特の美意識は、端正な人物像や画づくりに反映し、また原作の物語展開は成瀬固有の大胆かつ繊細なエロチシズムを導き出して、川端文学の映画化としても、成瀬巳喜男監督作品としても、第一級のものとなっている。俳優たちも持ち味を生かした素晴らしい演技で、とりわけヒロイン・原節子の匂いたつような美しさは忘れがたい。成瀬作品では清純な人妻や未亡人を演じている彼女であり、しばしば性的な含みが持たされるが、この作品ではそうした人妻という存在のなまめかしさが強調され、女学生のような三つ折りソックスをはいた普段着姿が卑猥なまでに官能的である。他に女を囲い彼女を顧みない夫の上原謙、義父役の山村聰もそれぞれ好演。
-
晩菊
制作年:
林芙美子の3つの短編小説『晩菊』『水仙』『白鷺』を一つにまとめて翻案した成瀬巳喜男監督の名作。それぞれのエピソードがユーモアのうちにほのかな哀感を漂わせて描かれる。とりわけ杉村春子扮する主人公が、以前燃えるような恋をした男の来訪を、最後の輝きを賭けて迎えるシーンには、男が金を借りに来たことを悟った杉村の心の動きが見事に表われて圧巻である。4人の中年女に、いずれ劣らぬ芸達者をそろえたことが作品に深みを加え、成瀬監督らしい色を出している。
-
驟雨
制作年:
岸田国士の一幕ものの戯曲数編を、水木洋子がまとめて脚色し、成瀬巳喜男が演出した小市民映画の名作。倦怠期にさしかかった夫婦が、様々な波紋に揺られながらも現在の生活の中に幸福を見出していく姿を、きめ細かな描写で綴っている。映画は新婚旅行から戻ったばかりの親戚の娘の来訪で始まり、夫への不満をぶつける娘に、二人がそれぞれの立場から反論することで、夫婦間の微妙なズレが示される。続いて二人の家の隣に若い新婚夫婦が越してきて、物語は両家をお互い映し合う形で展開していく。空間の造型にもこうした劇的構成が反映され、敷居をはさんで向かう妻と夫、生け垣を隔てて隣り合う2軒の家などの計算された配置が見事である。また、玉井正夫による神業のようなカメラが捉えた、夕立の場面での闇の中にかすかに浮かぶ原節子のクローズアップは、ラストで紙風船を打ち合う夫婦の上に広がる晴れわたった空とあざやかな対照をなし、比類ない美しさをたたえている。
-
女の座
制作年:
名優・笠智衆が主演した成瀬巳喜男監督作品。正月興行らしい豪華キャストで、家族制度における妻の立場を問う。家庭の中で唯一の他人ともいうべき長男の未亡人が、義理の両親を理解するというラストに、小津の「東京物語」へのオマージュが感じられて微笑ましい。
-
娘・妻・母
制作年:
井手俊郎と松山善三のオリジナル脚本を、成瀬巳喜男が演出。山の手の中産階級の一家が、金銭面の問題から家族の間に亀裂を生んでいく様を、オールスターで描く。劇中で主人公たちが撮る8ミリで、映画のトリックが暴かれるシーンが興味深い。
-
鰯雲
制作年:
成瀬巳喜男監督が初めて手がけたカラー・ワイドスクリーン作品。和田伝の同名小説を社会派の橋本忍が脚色、東京近郊の農村問題を扱っている。女性映画を得意とし、都会の下町を好んで描く成瀬監督としては異色の題材ながら、田園風景の叙情豊かな描写が秀逸だ。
-
黒い画集 寒流
制作年:
松本清張の原作を鈴木英夫監督、池部良主演で映画化。某銀行池袋支店長・沖野は料亭の女主人・奈美を見染め関係を持つが、上役で同窓生の桑山がそれを知る。桑山は沖野を左遷し奈美をものにしようとするが……。池部良が嫉妬に狂う中年男を熱演。
-
長屋紳士録
制作年:
太平洋戦争後の映画界では軍部による統制が解かれ、軍政批判の題材を取り上げる映画作家が続出したが、小津はそんな風潮には迎合せず、サイレント期の「出来ごころ」「浮草物語」「東京の宿」などの坂本武を主人公とした“喜八”ものを取り上げた。だがここでは喜八本人はむしろ脇役で、相手役の“かあやん”が主人公となっている。荒廃した焼け野原の東京を舞台に、親にはぐれてしまった子供が長屋に連れて来られる。人々はグチをこぼしながらも次第にその子供と情が通じるようになり、やがてその子は長屋になくてはならない人気者になる。しかしある日子供の父親が姿を現した……。ほのぼのとした人情とユーモアにあふれる作品であり、小津安二郎監督の作品のなかでも、最も温かい感情に満ちた一編と言える。笠智衆ら長屋の連中が酔っぱらって“のぞきからくり”の口上を歌いはじめるシーンのにぎやかな盛り上がりは抱腹絶倒もの。
-
大奥絵巻
制作年:
11代将軍・徳川家斉は、愛妾に町家育ちの純真な娘・お阿紀を選ぶが、大年寄らの激しい嫉妬を買い苦境に追い込まれる。叙情派・山下耕作監督が、溝口健二の愛弟子・成沢昌茂の脚本を得て、腰のすわった演出を見せる。
-
大菩薩峠 竜神の巻
制作年:
京の島原での宇津木兵馬との対決の後、机龍之助は天誅組と行動をともにする。そのとき追っ手の投じた爆薬のために盲目となり、竜神の森へと逃亡。しかし、またしても兵馬に挑まれた龍之助は、断崖から足を滑らし滝壷へと姿を消す。DVDは「大菩薩峠 DVD-BOX」に収録。
-
朱雀門
制作年:
公武合体を策す幕府により、貴公子、有栖川宮との結婚を控えながら将軍家茂への降嫁を余儀なくされた皇女、和ノ宮。和ノ宮と18歳の春まで起居をともにし、その気持ちがよく分かる侍女の夕秀だが、しかし有栖川宮に人知れず想いを寄せてしまう。有栖川宮もまた、夕秀の情熱と魅力の虜になる。悲恋メロドラマ。
-
浮雲〈1955年〉
制作年:
成瀬巳喜男監督の代表作であり、世界映画史に燦然と輝く名作中の名作。原作は成瀬がその出世作「めし」(1951)以来、「稲妻」(1952)、「妻」(1953)、「晩菊」(1954)と立て続けに映画化して成功した林芙美子の同名小説。戦時中、赴任先のインドシナで愛し合った妻ある男を追って引き揚げてきたゆき子は、次から次へと女を変える相手の自堕落さに、一時は外人相手の娼婦にまで身を落とすが、別れることができない。二人で新しい生活を始めるべく旅立った小島でゆき子は男に見とられながら病死する……。起伏の激しい物語展開でありながら、成瀬の冷徹な対象凝視の姿勢は一貫しており、主人公を演じる高峰、森の緊張感みなぎる絡み合いを捉えて、その演出スタイルは一つの頂点に達したといえる。地の果てまでも男を追うヒロインは、映画が描き得た最も鮮烈な女性像の一つであり、女優・高峰秀子の名は永遠に映画史に刻まれた。小津安二郎の言葉“俺にできないシャシンは溝口の「祇園の姉妹」と成瀬の「浮雲」だ”はあまりにも有名。
-
流れる
制作年:
幸田文の同名小説を映画化した成瀬巳喜男監督の名作。「めし」「晩菊」の名コンビ、田中澄江と井手俊郎が脚色を担当、東京の下町にある芸者置屋を舞台に、住み込みの女中の目を通して花柳界に生きる女たちの姿を描いている。出演は、18年振りに復帰した日本映画草創期の大スター・栗島すみ子をはじめ、女中役の田中絹代、女将の山田五十鈴とその娘・高峰秀子、そして芸者を演じる杉村春子、岡田茉莉子、中北千枝子とまさにそうそうたる顔ぶれ。こうした大女優の競演に際し、成瀬の演出は、派手で大仰な芝居よりはむしろ抑えた演技を要求しており、それにより各人の持ち味が十二分に引き出されて緊張感を高めている。衣装や小道具にも細かい配慮がなされ、女優たちの魅力と相まって実に印象深い。女優の芸と個性がぶつかり合い絡み合った、白粉の匂いにむせかえるような、まさしく女の世界である。
-
不知火検校
制作年:
勝扮する徳の市は、意地汚なく貯め込んだ金を旗本の若奥様に貸し、その弱みにつけこんで犯す。彼は師の検校を殺し、自らが成り代わり悪業の限りをつくすが、ついには役人に捕えられる。ピカレスク時代劇の佳作。勝の盲目の演技は、のちの“座頭市”への布石ともいえる。
-
秋立ちぬ
制作年:
女性映画で名高い成瀬巳喜男監督が、前年の「コタンの口笛」に続いて子供を主人公にした作品。父親を亡くして母の実家に引きとられた少年と近所に住む妾の娘との淡い交流を描く。少女の描写に、のちの成瀬映画のヒロイン的要素がうかがわれ、興味深い。
-
杏っ子
制作年:
室生犀星の小説を翻案した成瀬巳喜男監督の名作。高名な作家の娘が文学青年と結婚するが、夫が自分の才能を信じて売れない小説を書き続けるため生活が困窮し、夫婦仲も冷めていくという物語を成瀬独特の淡々とした作風で描いている。暗く起伏に乏しい内容でありながら、その映画的展開は圧倒的に素晴らしい。名声は天地の開きがありながら、同じ志を抱く作家としてのライバル意識を燃やす杏子の父と夫が、庭に隔てた障子越しに執筆中の互いの姿を気にし合うシーンなど、さりげないドラマの肌合いを捉える成瀬演出の白眉である。物語とは直接関係のない細部の卓抜な描写も印象的。
-
舞姫〈1951年〉
制作年:
川端康成の同名小説を映画化した成瀬巳喜男監督作品。バレエ教室を営む中年女性が愛情の冷めた夫と別れて新たな人生を歩もうとするが、結局もとの生活に戻るまでを香気豊かに描く。これがデビューの岡田茉莉子が美しく、早くも大女優の風格を備えている。
-
夜の流れ
制作年:
花柳界に生きる雇われおかみと、大学へ通うその娘との確執を描いた女性映画。古い世代の人物が登場する場面を成瀬巳喜男、若い世代の場面を川島雄三が担当するという、かつてない共同監督が試みられた。若者たちが大騒ぎするテンポの早いシーンと、母娘の情感が通い合うしっとりとした場面との対比が興味深い。
-
暴力の街
制作年:
敗戦後の混乱期に埼玉県下の地方都市で、実際に起こった事件をルポルタージュした朝日新聞記者の原作『ペン偽らず』をもとに、この作品のために作られた製作委員会が映画化した。暴力と金で町を支配するボスの一派と新聞記者や市民たちが闘う。東宝、松竹、大映など映画会社の枠を越え、広く劇団関係の俳優までが出演し、全国に市民の団結の力を知らせて共感を呼んだ。
-
日本侠客伝 雷門の決斗
制作年:
浅草の興行街。堅気となった聖天一家の持ち小屋・朝日座は、仇敵・観音一家の手に渡った。聖天一家改め平松興業の二代目・信太郎は、日本一の浪曲師・梅芳を招き挽回を図る。が、再起の機会をことごとく観音一家に潰され、信太郎の辛抱も限界に……。
-
緋牡丹博徒・お竜参上
制作年:
浅草の鉄砲久一家にワラジを脱いだお竜は、鉄砲久の娘婿が持っている興行権を鮫州政一家が狙っていることを知り、悪どい鮫州政のやり口を封じるために、渡世人・青山常次郎とともに殴り込む。加藤泰が監督した第3作「花札勝負」の後日譚的なストーリーで、藤純子の静と動の美しさが見事にスクリーンに焼きつけられた。特にお竜が菅原文太扮する流れ者のヤクザ・青山常次郎を見送り、そっとミカンを渡す雪の今戸橋のシーンは、圧巻。藤純子は何者にも代えがたい情緒を見せた。加藤泰の演出が、すみずみまで行き届いたシリーズ屈指の最高傑作である。
-
薄桜記
制作年:
五味康祐の新聞連載小説を市川雷蔵主演で映画化した正統派時代劇の名作。丹下典膳は留守中最愛の妻が、知心派の5人組に犯されたことを知り苦難の末、5人を捜し出し復讐を果たすが、自らも傷つき妻とともに果てる。この典膳と、勝新太郎扮する中山安兵衛との交友を絡ませ、二人の剣士の明暗を赤穂浪士の討ち入りを背景に映し出した内容になっている。森一生の重厚な演出と本多省三の華麗なカメラワークが、非業の最期を遂げた剣豪・丹下典膳の半生を浮き彫りにする。特にラスト、片手片足に深傷を負い戸板に寝かされながら、多数の敵と必死に闘う丹下典膳のデカダンスな美しさは筆舌につくしがたいものがある。丹下典膳に扮した市川雷蔵が素晴らしい演技をみせ、彼の代表作となった。
-
いれずみ半太郎
制作年:
博奕もさることながら腕っぷしも強い渡世人・半太郎。ワラジを脱いだ小田原で、男にだまされ身投げをしようとしていた宿場女郎・お仲を救う。お仲は半太郎のあとを追うが、彼女に逃げられた当地小田原の親分・原の嘉十も黙ってはいなかった。美男スター・大川橋蔵と丘さとみの主演コンビによる股旅もの。
-
妻
制作年:
巨匠・成瀬巳喜男監督による「めし」「稲妻」に続く3度目の林文学の映画化。短編小説『茶色の目』を原作に、結婚10年になる平凡なサラリーマンの冷えきった夫婦生活を描く。華麗な令嬢役で名高い高峰が醜悪な妻を熱演、それを受ける上原の抑えた演技も見事。
-
女の歴史
制作年:
一人の女の半生を描いた成瀬巳喜男晩年の作品。めまぐるしい時間の交錯の中、高峰が戦時中の娘時代から老け役までを好演。夫の死後、真に想いを寄せる男性の出現に揺れ動きながらも、その愛をあきらめるというヒロイン像に、成瀬メロドラマの真髄が見いだせる。
-
日本侠客伝
制作年:
舞台は深川木場。木場政組と新興の沖山運送との間には衝突が絶えなかった。木場政は小頭・辰巳の長吉を中心に巻き返しを図るが、悪らつな沖山は政治家や警察を抱き込み、木場政を潰しにかかる。見かねた木場政の客分・清治は単身沖山に乗り込むが……。
-
乱れる
制作年:
松山善三のオリジナル脚本を成瀬巳喜男監督が演出した名作。子供もいないままに夫に死別して以来、嫁ぎ先の一家をきりもりしてきた未亡人が、年の離れた義理の弟の純粋な愛の告白に揺れ動く姿を描く。かつては批判の対象にもなったが、横幅を十分に使いきらない禁欲的なワイドスクリーンの用法が見事な効果をあげ、一つ屋根の下に住み、互いに意識し合いながら周囲から孤立する男女が広い部屋の中央にぽつんと立ちつくす姿など、たぐいまれな緊張感に満ちている。複雑な女心を表現する高峰の演技はいつもながら素晴らしく、当時、人気絶頂期の青春スター・加山雄三の見違えるような繊細さも魅力である。
-
大阪の女
制作年:
八住利雄原作の連続TVドラマ『女神誕生』を巨匠・衣笠貞之助が映画化。大阪の焼け残りの一画に暮らす上方落語や漫才の芸人たちの群像を、人情味豊かに描く。大映カラーが捉えた大阪の歓楽街のにぎわいや、華やかなステージの光景が見もの。京マチ子、中村鴈治郎をはじめ、名優たちの芸が冴える。
-
眠狂四郎 勝負
制作年:
シリーズの実質的な出発点となった秀作。三隅研次の演出により風格ある仕上りをみせている。ある年の正月、狂四郎が偶然知り合った老人は幕政改革に燃える勘定奉行だった。彼は、将軍の子・高姫の御化粧代二万両を支給停止にするなどの政策で、幕府の特権階級やその取り巻きから命を狙われていた。老人の人柄に惹かれた狂四郎は、彼の命を守るため高姫の一味と斬り結ぶ。謎の女に操られた刺客たちとの決闘、柳生との御前試合など見せ場も数多い。また二八そば屋の呼び声や正月の風物などの江戸情緒が詩情を添える。狂四郎の人物像はより虚無的になり、もはや、いささか一徹な、かの老人にしか心を開かない。
-
弁天小僧
制作年:
河竹黙阿弥の歌舞伎狂言を題材に、伊藤大輔が監督した娯楽時代劇の佳作。弁天小僧をはじめとする白浪五人男は悪徳旗本を出し抜き、大名や商人から大金を奪い、悪人に操を狙われた町娘の危機を救う。町娘に扮した、青山京子の好演が光る。
-
お嬢吉三
制作年:
自分たちを牢にぶちこんだ悪旗本、原田にお礼参りを済ませたお嬢、お坊、和尚の三人吉三は、旅に出た。そこで借金のカタに売られた幼なじみのお美和と出会うお嬢。彼は、お美和を救い出そうとするが、彼女は原田のもとに妾奉公に出ることになり、3人は再び江戸に舞い戻る……。市川雷蔵主演の娯楽時代劇。
-
花咲く家族
制作年:
夫の死後、女手一つで3人の兄妹を育ててきた篤子は、長男の嫁と折り合いが悪い。次男の嫁こそは自分の気に入った娘をと考え、親戚の娘を田舎から呼び寄せるが……。子供たちを想う一念から息子たちを束縛してきた母親が、やがて若い世代への理解に目覚めていく姿を描いたホーム・ドラマ。
-
戦後最大の賭場
制作年:
東映任侠映画を代表する監督・主演の組み合わせの決定版。群雄割拠する任侠団体が大同団結して大日本同志会を結成するが、関西代表の組長が急死。そのあと釜を岩佐という男が狙うが、彼のあまりに卑劣なやり口に、部下の五木は反逆の刃を向ける。
-
切られ与三郎
制作年:
市川雷蔵の与三郎、淡路恵子のお富で『与話情浮名横櫛』を映画化。有名な源氏店のゆすり場はむしろさらりと描かれ、与三郎にひたむきな恋心を寄せる義理の妹との顛末に伊藤大輔らしい哀感が漂う。宮川一夫の撮影も魅力。
-
おかあさん
制作年:
全国の小学生が書いた作文に着想を得た水木洋子のオリジナル脚本を成瀬巳喜男が演出した名作。都会の下町に暮らす一家が世帯主である父親を病気で亡くし、母を中心に困難な状況を生きる姿を綴っている。導入部における作文の朗読のようなナレーションによって物語は長女の視点をとり、日常の小さな出来事や人々の微妙な心の揺れが、思春期の少女らしい鋭敏さで細やかに捉えられる。父親の死、里子へ行く次女との別れなどの不幸な事件をも劇的な誇張を排して淡々と描く成瀬監督の作風は、その繊細さゆえに豊かな情感を生み出し、登場人物への親愛の情をかきたてられずにはおかない。
最新ニュース
-

ヒュー・ジャックマン×ケイト・ハドソン『ソング・サング・ブルー』、4.17日本公開 愛と音楽が巻き起こす“ある夫婦”の感動の実話
-

『北方謙三 水滸伝』壮大な群像劇に心震わされるファイナル予告が解禁 木村達成による読書連載企画も発表
-

「実質ニチアサ!」10月スタートドラマ『俺たちの箱根駅伝』は仮面ライダー&スーパー戦隊出身イケメンが目白押し
-

『冬のなんかさ、春のなんかね』第4話 “文菜”杉咲花、売れっ子小説家の元カレと再会
-

『ラムネモンキー』第4話 “紀介”津田健次郎たち、中学時代の因縁を抱えて不良のリーダーのもとへ
-

『未来のムスコ』“将生”塩野瑛久の不器用な優しさに「好感度アップ」「意外にかわいい」の声
-

「ガチでムリ」異例解雇から4年のグラビア美女、レアな純白ワンピ姿に反響
-

「どうしたの?」「ビックリ」“梨園の妻”、突然のビジュ激変にファン仰天
-

『再会』「署までご同行願えませんか?」まさかの人物に任意同行 ネット衝撃「アリバイが崩れた!」「犯人?」(ネタバレあり)
-

「ゴチ27」新メンバー・倉科カナ、キュートな制服姿を初公開「佐野さんには負けたくないかな」
-

木村拓哉、『教場』舞台あいさつでポップコーン配るサプライズ 急接近に歓声
-

アカデミー賞大量ノミネート『罪人たち』『ワン・バトル・アフター・アナザー』凱旋上映決定!
-

「パチンコしてる時より楽しい」有名俳優が思わず本音
-

27歳妻&53歳夫の“年の差26歳”夫婦 出会いは小3 馴れ初めに驚き!
クランクイン!トレンド 最新ニュース ›
おすすめチケット
おすすめフォト
おすすめ動画 ›
最新&おすすめ 配信作品 ›
注目の人物 ›
-

X
-

Instagram