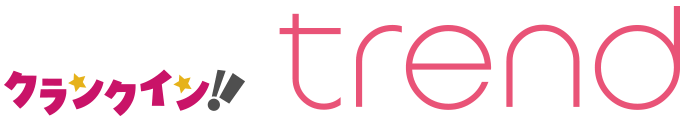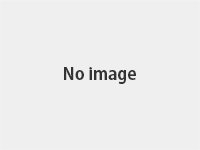原節子
出身地:神奈川県
生年月日:1920/6/17
原節子 出演映画作品
-
光と影(前・後編)
制作年:
松竹大船のシンボル的存在だった島津保次郎の東宝移籍第1作。防疫技師・弘吉とその許婚・佐保子、そして弘吉とふとしたことで親しくなった峰の三角関係を中心とした、ラブ・ストーリー。佐保子役は、当時から将来を嘱望されていた原節子。島津としては松竹時代ほどの才能が発揮出来なかった作品とされる。
-
二人の世界
制作年:
映画監督・島津保次郎が主宰していたシナリオ塾の塾生・塚原靖と山形雄策が内輪で書いたオリジナル・ストーリーを、山形が脚色して映画化されたもの。技術革新のため研究室の拡充を求める若手技師と、それに反対する重役陣の間で、板ばさみとなって苦悩する技術部長の姿を描いた、島津としては珍しいジャンルの作品。
-
熱風
制作年:
戦争の勝利の鍵といわれた鉄の生産増強をテーマに、銃後の産業戦士たちの決死の努力を描いた戦意昂揚映画。“赤いセシル・B・デミル“こと山本薩夫監督までもが、このような作品を作らされていたことに驚く。皮肉なことに、彼はこの時代のPR色の強い作品群によって、その名を大いに高めていった。
-
続々大番 怒涛篇
制作年:
第2作が製作されてから1年たたないうちに作られた。前2作と同じスタッフが集まっている。昭和13年、借金だらけの丑之助は百姓になろうと故郷へ帰るが、ヤミ商売に手を出す。しかし、運命は再び彼を株の世界に引き戻す。豪華な配役陣も前作から引き続いて出演、映画はヒットし続けた。
-
兄の花嫁
制作年:
見合い結婚をした銀行員・原田浩と下町育ちの春枝。だが浩の妹・昌子は、一度の見合いで結婚を決めた兄の感覚に理解しがたいものを感じていた。一方、春枝の母や祖母は、原田家の家風に早くも違和感を持ち始める。ところが、当の浩と春枝はそんな周囲の心配をよそに幸福な結婚生活にひたっていて……。小市民ものの巨匠・島津が戦時中にもかかわらず、なお自分の本領にこだわろうとした作品。
-
路傍の石〈1960年〉
制作年:
明治末期。吾一少年は成績優秀だが、借金のかたに奉公に出される。その家の子女、秋太郎とおきぬはかつての同級生。二人は主人とともに吾一につらくあたるのだった。まもなく母のおりんが病で死ぬが、家を出たまま父は帰ってこなかった。すべてに幻滅した吾一は、新たな人生を求めて東京行きの列車に乗る……。
-
麗人
制作年:
原節子と藤田進の名コンビによる戦後第1作のメロドラマ。没落華族の娘・圭子は、資本家と政略結婚させられるが、やがて彼の非道な経営方針に気づき、家を飛び出して労働運動家との恋とともに自由に目覚めていく。まさに原節子のために企画されたような、可憐なヒロイン像がはかなくも美しい作品だ。
-
女囚と共に
制作年:
他の娘と結婚した無情な男の新居に放火した女、前科11犯の窃盗犯、年若い夫を殺して乳幼児を抱えた女など、女子刑務所囚人たちの様々な生態を描き、その矯正補導を主題とした異色の社会派ドラマ。木暮・久我・岡田・香川らが女囚人を好演。
-
白雪先生と子供たち
制作年:
現場教師の原案をもとに、原節子がヒューマニストの女教師に扮して人間教育のあり方を問う作品。東京都の小学校教師の雨宮加代子は、校庭の池の鯉が最近しきりに盗まれ、子供たちの間で野蛮な言葉や賭けごとが増えていることに頭を悩ませている。子供たちを煽動しているのは、浮浪者の常治だった……。
-
日本誕生
制作年:
東宝が1000本製作記念映画として、稲垣浩監督、円谷英二特技監督、三船敏郎以下オールスター・キャストによって、日本の古来の神話を映画化した超大作。イザナギ・イザナミの国造りにはじまる神々の物語の中から、オトタチバナヒメとの悲恋に彩られた、ヤマトタケルノミコトの波乱の一生を中心に、高天が原の神々の饗宴、ヤマタノオロチ退治などが描かれ、クライマックスに天変地異の大スペクタクルが展開する。有名なエピソードが次々に登場するが、構成が単調でエピソード間の相乗効果を生まず、散漫な印象が残るのは否めない。しかし、円谷英二の集大成ともいうべき特撮の数々は見ごたえ十分。
-
女ごころ
制作年:
原節子と森雅之が、結婚して10年目の夫婦の倦怠と愛情の機微を演じる風俗ドラマ。伊曽子は夫・朝吉に若い愛人ができ、自分に友情しか感じないと言われ、“試験別居“をすることを決意するのだが……。引退近くの原節子の生彩のなさとは対照的に、昼は出版社、夜はバーに勤めるドライな女を演じる団令子が魅力的。
-
母の地図
制作年:
東宝移籍後、不調がささやかれていた島津保次郎が、久々に持てる力を発揮したと評価された作品。没落した旧家・岸家の家族それぞれの人生模様を描いていく。杉村春子、中村伸郎、森雅之ら文学座のメンバーが顔を並べた、東宝映画としては珍しいキャスティングが見もの。
-
緑の大地
制作年:
日本で初めてのお産を終えて、中国大陸で運河建設を進める夫・洋一のもとに帰る初枝。だが初枝の乗船した船に同乗した女学校教師・園子は、かつて洋一が愛した女だった……。島津が初めて中国大陸を舞台とした作品で、青島ロケが行われている。この時代ならではの帝国主義的な内容だが、脚本はのちに日本共産党系の映画人として知られることになる山形雄策が担当している。
-
怒りの海〈1944年〉
制作年:
東京帝国大学の教授を兼任しながら、日本海軍主要艦のほとんどの製造を手掛け、やがて帝大総長になって1943年に没した、“軍艦の父“平賀譲をモデルにした伝記映画。ワシントン条約によって、国別に主力艦の比率を決められ、廃棄艦を撃沈するシーンが前半のハイライト。特撮監督は、円谷英二。大河内伝次郎が平賀に扮し、風格ある演技を見せた。
-
美しき母
制作年:
鉱山に手を出して失敗した父・富太郎。妻の光代と子供の日出夫は、以前女中だった喜代の家に厄介になることに。光代は製紙工場の女工として懸命に働き、日出夫も中学合格を目指して懸命に勉強する。しかし、入学試験の朝、父の危篤を知らせる電報が届いて……。夫と別れたくましく生きる母の姿を原節子が好演。
-
生命の冠〈短縮版〉
制作年:
蟹缶詰製作所を経営する恒太郎と鉄次郎の兄弟は、例年にない不漁に悩まされ、取引先との契約も危ぶまれている。口論しながらも打開策に力を合わせる二人だが……。戦前当時の検閲に、労使問題を十分掘り下げられなかったとはいえ、ある種ドキュメンタリー的な力強さも感じさせる一編。
-
三本指の男
制作年:
スクリーンに名探偵・金田一耕助が初登場した記念すべき第1作。原作は、これもまた金田一が初めて小説に登場した『本陣殺人事件』である。中仙道の旧家・久保銀造の姪・克子と、名門一柳家の御曹司・賢造との間に縁談が持ち上がる。しかし、謎の“三本指の男“から、これを邪魔しようとする脅迫状が舞い込んだ……。
-
誘惑〈1948年〉
制作年:
「象を喰った連中」「安城家の舞踏会」に続く吉村公三郎の戦後第3作目。青年代議士は、妻帯者ながら亡き恩師の一人娘の学業と生活を援助するうちに、愛を抱くようになる。ある夜二人は温泉宿に泊まるが、娘は許されざる恋から逃がれるように宿をあとにする。代議士の妻は死の床で二人の愛を許す――というメロドラマ。
-
嫁ぐ日まで
制作年:
島津保次郎の東宝移籍第2作。妻を若くして亡くした生方光三と、その代役として家事にいそしむ姉娘・好子。光三はやがて再婚するが、好子の方は妹の浅子と後妻との不和を心配して、好意を寄せてくれる青年からの求婚を断り、若き外交官と結婚する……。好子役を原節子が演じているのをはじめ、設定にも小津的なものが漂う一作。
-
青い山脈・続青い山脈
制作年:
ある地方の町。女学生の寺沢新子は現金の代わりに米を持たされて町の雑貨屋へ学用品を買いに行く。留守番をしていた学生・金谷六助はちゃっかり新子に御飯を炊いてもらう。そんなことがきっかけで新子と六助は交際を始めた。ある日、新子のもとにラブレターが届き、新子はそれを信頼する島崎先生に見せる。島崎は校医の沼田にこのことを相談する。学校では理事会が開かれラブレター問題の大論争。しかし実はラブレターは新子の同級生の仕業だった……。というあまりにも有名な石坂洋次郎の原作を今井正が演出したユーモア青春編。藤原釜足がラブレターを読み上げる有名な場面は何度観ても笑わせられる。DVDタイトルは「青い山脈 前・後篇」。
-
忠臣蔵 花の巻 雪の巻〈1962年〉
制作年:
東宝創立30周年記念映画で、殿中刃傷の背景を歪曲して描き新味を出した八住利雄のシナリオと、手持ちカメラでブレも構わず写実的効果を出した稲垣浩の演出が光る“忠臣蔵”。松本幸四郎(8代目)以下、東宝の映画・演劇の手持ちスターを総動員。
-
田園交響樂
制作年:
山本薩夫にとっては、成瀬巳喜男の助監督から監督になって3作目。A・ジイドの同名小説を翻案したもので、当時東宝きってのスターだった、原節子のために監督自らが立てた企画である。北海道の寒村の小学校長が、盲目の娘を引き取って育て、彼女は成長して感受性豊かな女性になり、校長の弟と恋に落ちていく……。カメラの宮島義勇と山本監督の初コンビ作で、海外ではジャン・コクトーにも評価されたと監督は語っている。
-
上海陸戦隊
制作年:
激戦のあとも生々しい上海にロケーションして製作されたドキュメンタリー・タッチの戦争映画。海軍陸戦隊の上海での活躍から陸軍大部隊の敵前上陸までを描く。熊谷監督は映画人のなかでも超国粋主義者として知られた人物。中国人避難民に扮した原節子の義兄でもある。
-
決戦の大空へ
制作年:
土浦海軍飛行隊予科練習生を時代のホープとして描き、その予科練がいかに素晴らしいかを訴えた戦意昂揚映画。学生の自由な映画鑑賞が禁止された1943年、数少ない国民映画普及会選定映画として子供たちの鑑賞が許された作品でもある。高田稔と原節子が「望楼の決死隊」に続いて、息の合うところを見せた。
-
阿片戦争〈1943年〉
制作年:
戦時中の時局に迎合して企画されたもので、イギリスの中国への不当な干渉・阿片戦争を題材にしている。しかし単なる国策映画に止まらず、D・W・グリフィス監督の「嵐の孤児」に想を得た、日本映画史のなかでも傑出のスペクタル史劇となっている。物語の舞台は1839年の中国で、阿片を流し侵略を計るイギリス側と、阿片から人民を守ろうとする清の役人・林則徐との虚々実々をめぐる戦いと、戦乱に巻き込まれて離れ離れになる悲劇の姉妹の物語を並行的に描く。美しい原節子と高峰秀子の姉妹に涙すると同時に、俯瞰で捉えられたミュージカル場面の素晴らしさにも心踊らされるバラエティーに富んだ作品。
-
望楼の決死隊
制作年:
日中戦争直前の鮮満国境における国境警察官たちの労苦と活躍を描いた戦意高揚アクション映画。新任国境警察官の目を通してドラマが語られていく。酷寒の国境のもと、原節子までもが銃を持ち、さながら西部劇のタッチで迫るアクション・シーンは圧巻だ。監督は、「ひめゆりの塔」の今井正。
-
東京暮色
制作年:
二人の娘を残したまま、母親が愛人と家出をしてしまった一家の物語で、戦後期の小津のフィルモグラフィーでは例外的に暗く、陰うつな雰囲気に包まれた異色の作品といえるだろう。しっかり者の姉、つまらぬボーイフレンドに妊娠させられ事故死する妹、妻に逃げられながら態度がはっきりしない父親、変転の果てに、ひっそりと麻雀荘を営む母親。小津監督は、それぞれのもの言わぬ肩や背中に生きることの悲哀をずっしりと感じさせ、寂漠の人生模様を甘い感傷に溺れることなく、見事に織り上げてみせた。とりわけ、母親と娘の再度の別れのシークエンスが激しく胸を打つ。
-
秋日和
制作年:
小津安二郎作品の家族劇では娘役として欠かせない存在であった女優・原節子が母親役に回った、小津晩年の傑作。夫を失ったばかりの秋子は、亡夫の友人たちに再婚を勧められる。彼女にはその気はないが、まだ美しい未亡人である母親が再婚するのではないかと、娘のアヤ子は気が気でない。母親の気持ちを誤解した娘は反抗し始める。やがて二人は和解し、いつの日か嫁いでいく娘をつれて秋子はささやかな二人きりの旅行に出かける……。亡夫の友人を演じた佐分利信、北竜二、中村伸郎のとぼけたやりとりがおかしく、岡田茉莉子の初々しさも印象深いが、何より母娘旅行のシーンの優しさが心にしみる。
-
巨人傳
制作年:
ヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』を映画化した、伊丹万作最後の監督作品。時代を幕末から明治維新直後に設定し、前科者で何度も脱獄を試みたものの失敗、19年の刑に処された大沼という男が、ついには役人を殺して脱獄に成功、時代の混乱に乗じて世の中を渡り歩いていく姿を描く。ある時、彼は不幸な少女・千代子を引き取り、育て上げていくのだが……。これまでにもゴルズワジーの『逃走』を翻案した「逃げ行く小平次」、モルナールの『リリオム』の翻案「金的力太郎」で多大な評価を得ていた伊丹が、再び『レ・ミゼラブル』を見事に日本の風土に展開した作品。この頃から闘病生活に入った彼は、以後、稲垣浩の「無法松の一生」「手をつなぐ子ら」など脚本を担当したのみで、ついに監督に復帰することなく、1946年、世を去った。
-
お嬢さん乾杯!
制作年:
木下惠介が「破戒」に次いで撮り上げた作品。木下としては初の本格喜劇である。敗戦による社会体制の変化に伴い華族制度は廃され、いわゆる“斜陽族”が登場し、その一方では新興成金が生まれたりした。そうした世相にアイデアを得て作られたのが本作品である。自動車修理業で成功した圭三に元華族の令嬢・泰子との縁談がもち上がる。圭三は“提灯に釣鐘だ”として最初は断わるが、仕方なくお見合いするハメになる。ところが圭三は泰子に会ったとたん一目惚れ。圭三には雲の上の美女に思われた泰子の方も結婚を承諾。こうして成金と没落華族のチグハグなやり取りが始まる。この明るく快テンポの都会喜劇は、封切り当時大ヒットした。
-
白痴〈1951年〉
制作年:
黒澤明が長年の夢であったドストエフスキーの名作を、舞台をロシアから北海道へ移し変えて映画化した野心作。善の権化である美しい亀田青年、彼を愛する二人の女・綾子と那須妙子、そして妙子を野獣のように愛する赤間伝吉の4人の間には、時には美しく時には神々しいまでの愛と激しい憎悪が燃えあがる。この作品は当初4時間25分の長さで前後編に分けて上映されることになっていたが、試写を見た松竹首脳陣が難色を示し大幅にカットされることに。それに激怒した黒澤監督が“切りたければフィルムを縦に切れ!”と怒鳴ったという逸話が残っている。結局ふた通りのバージョンが作られ、長尺版の3時間30分のものは東劇で3日間だけ公開、現在見ることができる2時間46分のものは、一般公開時のもの。
-
智恵子抄〈1957年〉
制作年:
詩人の高村は智恵子との出会いで、過去のすさんだ生活を清算し、生きる喜びを見出していく。しかし、二人の美しい愛の暮らしは長くは続かず、智恵子の精神は少しずつ狂い始める。原作の高村光太郎が病死して1年あまりの映画化で、話題を集めた。原節子が難しい役柄を好演している。
-
ふんどし医者
制作年:
長崎で和蘭陀医学を修めた主人公は徳川家御典医の考査のために江戸に上る途中、大井川の川止めに遭ったが、そこで病苦にあえぐ貧しい人々に接した。主人公は江戸へ上るのを止め、この町に留まることを決意する。日本が近代の夜明けを迎えた時代を背景に、医学をめぐって繰り広げられる人間の葛藤劇。
-
女であること
制作年:
川端康成文学の映画化。佐山弁護士と妻・市子は教養深い夫婦だが子供がない。家出してきた市子の旧友の娘の面倒をみることになったところから、波紋が広がっていく。ブルジョワ家庭とその周辺の人間模様を手堅くまとめている。
-
めし
制作年:
巨匠・成瀬巳喜男監督の初期の代表作。同名原作は林の未完の絶筆で、倦怠期にある夫婦がささいな出来事から次第に亀裂を深めていく様を描いており、脚色にあたっては、家を出た妻が夫のもとに戻り、平凡だが心安まる生活に幸福を見いだすという結末が補足されている。成瀬演出は、劇的で明快な主題を持つ物語を語るのではなく、日常生活のキメ細かい描写や、俳優たちの持ち味を最大限に引き出す手腕に高い評価が与えられているが、この作品にはまさにその真骨頂が見いだせる。ささやかで慎ましい夫婦の生活の匂いを感じさせる住居、妻を演じる原節子の微妙な表情の変化やたたずまい、それを受ける夫役の上原謙の抑えた芝居など、あらゆる要素が成瀬独特の作品世界を構成して圧巻である。名撮影監督・玉井正夫が初めて成瀬とコンビを組んだことでも重要な作品。
-
山の音
制作年:
原作は川端康成が戦後最初に発表した同名小説。とある中流家庭を舞台に、老境に入った男が、同居する若く美しい息子の嫁に抱く複雑な感情を綴っている。下町を愛し、市井に暮らす人々の日常を描いてきた成瀬の作品歴においては異色の題材。だが、日本的なものをめぐる川端独特の美意識は、端正な人物像や画づくりに反映し、また原作の物語展開は成瀬固有の大胆かつ繊細なエロチシズムを導き出して、川端文学の映画化としても、成瀬巳喜男監督作品としても、第一級のものとなっている。俳優たちも持ち味を生かした素晴らしい演技で、とりわけヒロイン・原節子の匂いたつような美しさは忘れがたい。成瀬作品では清純な人妻や未亡人を演じている彼女であり、しばしば性的な含みが持たされるが、この作品ではそうした人妻という存在のなまめかしさが強調され、女学生のような三つ折りソックスをはいた普段着姿が卑猥なまでに官能的である。他に女を囲い彼女を顧みない夫の上原謙、義父役の山村聰もそれぞれ好演。
-
驟雨
制作年:
岸田国士の一幕ものの戯曲数編を、水木洋子がまとめて脚色し、成瀬巳喜男が演出した小市民映画の名作。倦怠期にさしかかった夫婦が、様々な波紋に揺られながらも現在の生活の中に幸福を見出していく姿を、きめ細かな描写で綴っている。映画は新婚旅行から戻ったばかりの親戚の娘の来訪で始まり、夫への不満をぶつける娘に、二人がそれぞれの立場から反論することで、夫婦間の微妙なズレが示される。続いて二人の家の隣に若い新婚夫婦が越してきて、物語は両家をお互い映し合う形で展開していく。空間の造型にもこうした劇的構成が反映され、敷居をはさんで向かう妻と夫、生け垣を隔てて隣り合う2軒の家などの計算された配置が見事である。また、玉井正夫による神業のようなカメラが捉えた、夕立の場面での闇の中にかすかに浮かぶ原節子のクローズアップは、ラストで紙風船を打ち合う夫婦の上に広がる晴れわたった空とあざやかな対照をなし、比類ない美しさをたたえている。
-
娘・妻・母
制作年:
井手俊郎と松山善三のオリジナル脚本を、成瀬巳喜男が演出。山の手の中産階級の一家が、金銭面の問題から家族の間に亀裂を生んでいく様を、オールスターで描く。劇中で主人公たちが撮る8ミリで、映画のトリックが暴かれるシーンが興味深い。
-
晩春
制作年:
小津安二郎といえば、父と娘、あるいは母と娘など、平凡な家庭の日常を淡々と描いた作風で知られた作家だが、実はそういう家族劇は後期、脚本家の野田高梧と組んだ頃のものであり、初期にはギャング映画やコメディなど様々なジャンルを手掛けていた。そんな後期の小津スタイルが確立されたのがこの「晩春」である。北鎌倉に住む大学教授は、婚期を逃がしかけている娘を結婚させようとする。父を一人にはしたくないと、娘は結婚に乗り気ではないが、父は寂しさをこらえて娘を嫁がせるのだった……。父娘二人が、最後に水入らずで枕を並べて過ごす夜のシーンは特に有名で、壷の空ショットが挿入されることから“壷のシーン”として多くの評論家にとり上げられ、研究されてきた。余計なセリフや感情表現を用いず、その場の空気ですべてを語ってしまう小津演出の真髄がここにある。
-
ハワイ・マレー沖海戦
制作年:
太平洋戦争の幕開けとなった真珠湾の米軍艦隊奇襲攻撃と、マレー半島沖の英軍艦隊急襲の大戦果を記念し、大本営海軍報道部の企画によって製作された開戦1周年記念映画。ストーリーは海軍兵学校の一生徒と、彼を慕って航空兵に志願する従弟を軸に展開。前半部分は帰省した兵学校生徒と従弟の一家の交流と、予科練での厳しい訓練ぶりを描き、後半は、真珠湾とマレー半島沖の海戦に参加した二人の活躍を描く。特筆すべきは円谷英二らによるミニチュアを用いた特撮の素晴らしさであり、戦後の東宝特撮映画の技術的基盤は、この映画によって確立された。実際に予科練で撮影された訓練シーンは見ものだ。
-
ノンちゃん雲に乗る
制作年:
天才少女ヴァイオリニストとうたわれた鰐淵晴子の本格的デビュー作。木に登って枝が折れ、池に落ちたノンちゃんが雲の上の白ヒゲのおじさんに出会うというマジカル・ファンタジー。童話作家のベストセラーが原作で、当時の人気女優・原節子も出演。雲の上の世界を映像化したアニメ合成などの特撮も独創的。
-
麥秋〈1951年〉
制作年:
小津安二郎監督の力量が最も充実していた時期に作られた作品であり、「晩春」や「東京物語」など、小津の代表作と並べても決してひけをとらない素晴らしい出来で、小津の最高作とするファンも多い。戦前の小津のサイレント作品で数本の脚本を書いた野田高梧は、「晩春」以後小津との名コンビを続けていくのだが、そのセリフの間(ま)の絶妙さは本作で最大に発揮される。北鎌倉に住む間宮家の気がかりは、28歳になる独身娘・紀子の結婚だ。両親や兄夫婦は紀子の縁談についていろいろと心配するが、本人はあまり気のりでない様子。やがて兄妹のような気軽さでつきあっていた子持ちの男と結婚しようと紀子は決心する……。原節子、笠智衆をはじめ、相変わらず充実したキャストの存在感は大きいが、なかでも紀子の結婚相手の母を演じた杉村春子のコミカルさとシリアスさを使い分けた演技は抜群。
-
河内山宗俊
制作年:
情婦の居酒屋でむだ飯を食って暮らすヒモ・河内山宗俊。守銭奴の顔役・森田屋一家の用心棒の金子市之丞。二人は日々をのんびりと気ままに過ごしていた。二人のマドンナは、若いながらけなげに駄菓子や甘酒を売って弟を養っているお浪という娘。そのお浪が、弟の不始末の三百両の金のために森田屋や女衒(ぜげん)の毒牙にかかり、女郎に売られようとする。宗俊と市之丞はお浪を救うために命を懸けて戦うのだった……。若くして死んだ天才監督・山中貞雄の、現在残されたたった3本の作品のうちの一つ。市民の情緒を確かな演出で描ききった秀作である。また若き日の原節子がお浪役で初々しい演技をみせるのも見どころ。
-
続大番 風雲篇
制作年:
前作で大もうけした金も株の大変動で一文なしとなり、丑之助は故郷に帰る。故郷で平和な日々を過ごしていると、兜町に帰ってこいという連絡がくる。そして好景気に乗って株で大もうけするのだが、折からの日華事変で大暴落し再びスッテンテンになってしまう。加東のギューちゃんも2作目とあってのびのびと演じきっている。
-
わが青春に悔なし
制作年:
戦前の京大滝川事件と、戦中のゾルゲ=尾崎秀実のスパイ事件の二つをモデルに創作された反戦運動を描いた力作。“永遠の処女”原節子が若々しい雰囲気を画面に充満させている。当時は労働組合の発言力が強く、“天皇クロサワ”でさえ後半のプロットの書き直しを余儀なくされたという逸話が残っており、興味深い。大学教授の美しい娘・幸枝は学生たちの憧れの的だ。野毛と糸川は幸枝を争うライバルだが、野毛は反戦運動家に、糸川はそれを取り締まる検事にと正反対の道を選ぶ。幸枝は野毛と結婚するが、野毛は戦争妨害を指導した非国民として逮捕されてしまう……。女主人公の自我を強くうたい上げた女性ドラマの傑作になっている。
-
大番 完結篇
制作年:
大ヒット・シリーズも、ついに最終編。1949年に東京証券取引所が再開。故郷に帰っていたギューちゃんは、再びひと旗あげようと株に手を出した。結果は大成功。朝鮮戦争の特需景気もあって、ギューちゃんは大金持ちになる。その勢いで、可奈子未亡人に求婚するが、彼女は結核に倒れた……。原節子が薄幸のマドンナを好演。
-
愛情の決算
制作年:
今日出海の小説『この十年』の映画化。終戦後10年の日本人の家庭を、佐分利信の監督・主演で描いた。復員した楢崎は死んだ戦友の妻と結婚する。失業から特需ブームで再就職へ。やがて夫婦の愛情は冷えていく……。風俗史を交えた辛口ホームドラマ。
-
安城家の舞踏會
制作年:
安城家は、代々の名門華族。だが第二次大戦終結とともに、他の華族同様、没落の憂き目にさらされていた。家は抵当に入れられ、かつてこの家のお抱え運転手であった現運送会社社長からは令嬢・昭子に堂々と求愛される始末。これまでの価値観ではまったく通用しない時代がやってきたのである。そんな安城家の最後の舞踏会を通じて、180度違う新たな時代の到来を描いた、吉村公三郎の代表作。新藤兼人の脚本を得て、吉村は決定的な名声を確立する。全体にどこか日本離れした設定は、新藤が底辺にチェーホフの『桜の園』を利用したため。しかし、それがいささかも非現実的ドラマに陥らなかった点に、彼の真価があるといえよう。
-
小早川家の秋
制作年:
主として松竹で映画を作ってきた小津が、珍しく東宝で、しかも東宝主演級の俳優を多数出演させ撮り上げた作品である。造り酒屋の小早川万兵衛を中心に、小早川家にかかわる人々の悲喜こもごもを独特の情感で描写している。万兵衛の死んだ長男の嫁・秋子を再婚させようと、親戚連中は手を尽くすが、秋子はなかなか承諾しない。次女・紀子は転勤した同僚への恋を断ち切れずにいる。一方、妻に先立たれた万兵衛は、昔なじみの妾とよりを戻し、人目を盗んでは通い詰めていた。妻の法事の日の夜、急に倒れる万兵衛。一時は回復するが数日後、妾の家でぽっくり逝ってしまう。親戚一同が会し、静かな葬式が営まれる。火葬場の煙突のけむりを人々がそれぞれの思いを抱いて見上げる名シーンの記憶が、伊丹十三監督の処女作「お葬式」に反映した。
-
東京物語
制作年:
黒澤明、溝口健二とともに日本を代表する映画作家・小津安二郎の代表作といえばこの「東京物語」につきるだろう。小津がサイレント期から描き続けてきた親子関係のテーマの集大成ともいえる作品である。地方から老いた夫婦が上京し、成人した子供たちの家を訪ねる。子供たちははじめは歓迎するが、やがて両親がじゃまになって熱海に行かせたりして厄介ばらい。戦死した息子のアパート住まいの未亡人だけが親身になって面倒をみてくれるという皮肉。やがて老夫婦は田舎に帰るが、その直後、妻は急死してしまう。一人残された老人は、静かに海を見つめて……。戦後の日本における家族生活の崩壊を描いた、と監督本人が語るこの作品は、人間の孤独感、死生観といったテーマまでをも取り込み、味わい深い作品となった。志賀直哉を深く愛した小津監督は、『暗夜行路』にちなんで尾道市をラスト・シークエンスの舞台に選んだが、その尾道の寂れて、どこか温かい風景が、この厳しいテーマを繊細に包み込み、忘れることのできない画面を生み出した。
最新ニュース
-

『俺たちの旅』シリーズがギネス認定! 中村雅俊も驚き「まさか自分たちが」
-

大倉忠義、アイドルと経営者の両立への考え明かす「後輩に恥じない姿でいなきゃいけない」
-

45歳のジゼル・ブンチェン、昨年誕生した赤ちゃんの写真をシェア 柔術トレーナーと12月に再婚
-

筧美和子、第1子妊娠を発表「無事に生まれてきてくれることを願いながら」
-

「目のやり場に…」稲村亜美、肩ひも極細なキャミ姿で海外満喫「芸能人の中で一番美人」
-

ティモシー・シャラメ、カーダシアン家での愛称が明らかに 恋人カイリーの姉が暴露
-

マーゴット・ロビーの姿に会場が釘付け! 圧巻のグラデーションドレスで魅了
-

主演・ムロツヨシ『ドラフトキング』続編5.15放送決定 スカウトマン郷原が再び全国に埋もれる原石たちを磨き上げる
-

竹野内豊、眉なし・ヤクザ役で別人のような姿に Netflixシリーズ『ガス人間』ビジュアル公開
-

ケンドーコバヤシが結婚&第1子誕生を発表 報道陣へ“重ね重ね”お願いも
-

『ほどなく、お別れです』目黒蓮の所作が美しい“納棺の儀”、本編映像解禁 浜辺美波も「見入ってしまいました」
-

唐田えりか、『浮浪雲』で時代劇初挑戦! 「ドキドキワクワクしていました」
-

“歴代レッド”中尾暢樹・小澤亮太・高橋光臣がVシネ『ゴジュウジャー VS ブンブンジャー』にゲスト出演決定 コメントも到着
-

眉ブリーチに透明ポンチョ、抗議バッジ…サンダンス映画祭で視線を集めた三者三様ルック
クランクイン!トレンド 最新ニュース ›
おすすめチケット
おすすめフォト
おすすめ動画 ›
最新&おすすめ 配信作品 ›
注目の人物 ›
-

X
-

Instagram